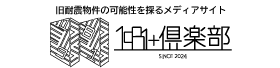VINTAGE
ヴィンテージ物件の魅力
「再生をデザインする」建築家 渡邉明弘
「再生をデザインする」
建築家 渡邉明弘氏
―渡邉さんは、どんなふうに建築家を志されたのでしょうか。
熱心に勉強もしてなかったので、高校卒業後は入りやすい地元の北九州市立大学に入ったんです。あまり考えずに建築の学科を選んだら、当時は既に新しく建てていく時代は終わりつつあり、どちらかというと『人の減少とともに建物が余って、しかも古くなっていく』という時代でした。周りより遅れて大学の途中から建築が面白くなり始めたものの、大学時代に教わった先生や建築家の方からは「建物が足りていない時代に求められた建築家の社会的使命は終わったよ」という雰囲気を感じていました。じゃあこの先自分はどんな建築家を目指せば良いのかと悩みながら進学した首都大学東京(現東京都立大学)の大学院で、リファイニング建築という再生手法を提唱していた青木茂さんという建築家の教授に出会いました。そこで、今ある旧耐震の建物を再生したり、補強して再利用する再生手法を学んだんです。これからの時代は、既存の建築を再生させるような建築家が必要とされるに違いないと直感し、青木さんの誘いもあって卒業後は青木工房に就職しました。青木さんが研究室を持っていたのは2年間だけだったので、大学と事務所の両方で師事した建築家は僕だけになってしまいました(笑)。
 渡邉明弘建築設計事務所 建築家/渡邉明弘氏
渡邉明弘建築設計事務所 建築家/渡邉明弘氏©1981+倶楽部
―それもあって、卒業後は再生建築の分野で仕事を始められた、と。
再生に進んだ理由は2つあって。ひとつ目はある種の逆張りです。前述したように僕が就職した10数年前は「この先、更地から建てていく仕事はどんどん減っていくだろう」という世の中だったんです。それでも、優秀な学生たちの多くは新築をたくさん建てている建築家の事務所に就職しようとする傾向にあり…つまり、市場がどんどん小さくなっていくところに優秀な人材が集まっていこうとしていました。でも、縮小するレッドオーシャンに飛び込んでいくのはどうなのか、と。それに対して、再生は今以上にニッチな分野でしたが、将来的には市場も大きくなって、社会的意義も増えていくだろうと読んでいました。建築家の主戦場とは正直言い難い状況でしたが、だからこそ自分の活躍の場もあるかもしれない、と考えました。そしてもう1つは、新築とは違う建築の作り方、デザインができるんじゃないか、という新しい建築の可能性みたいなものに僕自身が惹かれていったのもあります。新築を建てる時とは設計のプロセスも全く違いますし、必要とされるスキルや技術体系も大きく異なりますが、だからこそ新築とはまったく違う再生ならではの建築が出来上がることに面白さを感じるようになっていきました。
―2016年に設立された、AWA(渡邉明弘建築設計事務所)では『新築では得られない建築』を志向されています。もう少し具体的に渡邉さんが感じられている『新築では得られない建築』の面白さ、魅力を教えてください。
いくつかある中で、僕が一番面白いと感じているのは、形の読み替えができることです。僕たちが学んだものの作り方やデザインって、「合理的で機能的なもの」が良しとされていたというか。モダニズム や合理主義という価値観を下敷きにしていて、特定の使い方に最適な形や素材、寸法を考えることが前提とされているんです。実際、病院だったら病院に適した形、学校なら学校に、お店ならお店に適した形がそれぞれにある、と。でも、再生の建築というのは、もともとあるもののために作られていた形を別の形に転用することですから、新築のように新しい用途に基づいてベストな形を作る、というわけにはいかない。つまり、既存の建物を読み替えることで新築では作れないものを作れることが、再生ならではの面白さかなと感じています。
―今回取材に使わせていただいたREDO JIMBOCHOも渡邉さんが設計をされて、GOOD DESIGN AWARD BEST100に選ばれました。このビルを設計される上ではどんなところに留意されましたか。
ここの設計は他の建物とは違って少し特殊だったんです。というのも、通常、設計のご依頼をいただく際は、例えば100人入院できる病院にしてほしい、とか、300人が働くオフィスにしたい、と言うようにクライアントさんの明確なリクエストがあるんです。でも、REDO JIMBOCHOは、キーマンさんが購入されて耐震補強を行った上で、利用方法はこれから考えていかれるということでした。それもあってどんな使い方をするのかという事業計画と、設計、デザインといった建築計画が同時に進んでいきました。例えば1階部分をお店にするなら四角いビルの形を活かしてコの字型のカウンターにした方が、シェフの動線を考えても合理的だよね、とか。逆にこのデザインなら他にもこんな事業ができるかも、というように。また、3〜5階はシェアハウスになったのですが、1フロアの占有面積が40平米くらいの建物なので、普通の間仕切だと1フロア3部屋くらいが限界なんです。ただ、クライアントさんとしてはビジネス面を考慮すると1フロアで4部屋は欲しい、と。それを受けて、最終的には三角の部屋をご提案しました。それによって新築ではまず考えないような部屋が完成したのですが、入居者の方にはそこに面白さを感じていただいているのか、常時、満室の状況が続いていると伺っています。
 GOOD DESIGN AWARD2024 BEST100 REDO JIMBOCHO
GOOD DESIGN AWARD2024 BEST100 REDO JIMBOCHO©株式会社キーマン
―外観的にも、神保町の街に溶け込んでいるのも印象的です。
ありがとうございます。神保町というのは古い建物が修繕されながら長く残っている地域と、そういった小さいビルが建ち並ぶ区画をいくつかまとめて再開発をした地域が、隣り合っているエリアなんです。そんな街並みに建つこの建物を初めて見にきた時は、小さな古ビル等が<修繕>か<再開発>のどちらかの未来を選択するよう迫られているように感じられたのをよく覚えています。だからこそ、初めてこのビルを見た時は、そのどちらでもない再生ならではのあり方、立ち姿を見せられたらいいなと思っていました。それもあって外観の意匠も、もともとの吹付の塗装を撤去して、クラックの補修をするだけにとどめたんです。そこに化粧板を貼ったり塗ったりすると『新築そっくり』みたいな建物になってしまうからです。それに、限りなく新築に近づけるのでは、新築がベストであり改修は新築の下位互換だと言っているのと同じだな、と。そんな思いもあって、敷地単位で<再開発>する新築(そっくりのような改修)なのか、反対に<修繕して>ノスタルジーに訴えるのか、という軸とは全く別のベクトルで世界観を表現しようと考え、剥がしっぱなしの意匠にしました。
―既存の街の風景や歴史を大切にしながら、唯一無二の建物に蘇らせることができるのも再生建築の良さだと感じます。
建物って基本的には長く、いろんな人が使っていくものですからね。どの建築も、完成直後のピカピカの状態を維持し続けるのはそもそも不可能だと思うんです。まして、建物単体ではなく、街と一緒に使われて生きていくものだからこそ、ピカピカの状態を良しとして考えるのは違うんじゃないか、とも思います。であればこそ、いろんな要素を同居させて、街に馴染ませていくことも、僕は建築の1つのあり方なんじゃないかと考えています。実際、REDO JIMBOCHOも実は天井の塗装部分は、前の方が施工された時のままの状態で残していますし、床も敢えて貼っていないというように、もともとの状態を残しているところがちょこちょこあります。
―渡邉さんが学生の頃は再生建築に興味を持たれる方も少なかったということですが、最近は興味を持たれる建築家の方も増えてきたのでしょうか。
 ©1981+倶楽部
©1981+倶楽部―逆に、長く再生建築に携わってこられたからこそ、見えてきた課題はありますか?
世の中でも少しずつ再生への理解が深まりつつある一方で、まだまだ新しいものがいい、新しい方が安心という価値観は拭いきれてはいません。そこをどう変化させていくのかは課題の1つだと思っています。というのも、新しいのがいい、新しい方が安心というような価値観がある限り、再生の建築も「新築に限りなく近づけた方がいい」という価値観になってしまうからです。そうなると…先ほどもお話しした通り、どこまでいっても新築の下位互換でしかなくなってしまいます。そうではなくて、再生ならではの価値観、豊かさや面白さみたいなものが受け入れられたり、愛される世の中になっていけばいいなと思っています。
―渡邉さんが感じられている再生建築の『豊かさ』を教えてください。
昔からいろんな人の手を渡ってきたものに囲まれて僕たちは生活をしている、という事実への気づきみたいなところかもしれません。長い時間軸の中で僕たちの過ごしている今があることを意識できるというか、時間や歴史に対する意識を持てるのも豊かさの1つにつながっていくのではないかと思います。
―この先、建築家として描いている野望があれば聞かせてください。
「再生をデザインすること」です。どういうことかと言うと、建物の再生は少しずつ注目され始めていますが、まだまだその価値は建て替えと比べた、現実的なメリットにばかり目が向けられているのが現状です。もちろんそれは大事な側面ですが、先ほどお話ししたように再生の価値ってもっと多様で創造的なものだと思います。だからこそ、そうした意識がスタンダードになっていけばいいなと思いますし、それを象徴するような建築が作れたら嬉しいです。そのためには僕だけが活動してもダメだと思うので、今後は建築家としての活動をしながら大学でも教えられたら、とも思っています。あとは、僕も時に新築物件を受けることもある中で、今お話ししたような再生ならではの面白さや、そこで発見したことを逆に新築の方でも活かせるようになっていけばいいな、とも思います。新築だけど、再生で見つけた豊かさを活かして図面をひく、みたいな。具体的なことはこれからなので、言葉にするのは難しいですが。
―温故知新と言いますか、古い建物にもヒントになることはたくさんある、と。
新築の合理的な考え方ってクライアントのリクエストに対するアンサーのところで、そのリクエストが変わることを想像していないことが多い気がするんです。もちろん、設計や施工が始まった時点ではその時点でのリクエストに最適化した建物になっているんですが、将来的な使い方を考えると、果たしてそれでいのか、と。つまり、建物の寿命は人や事業の寿命よりも長い、ということを考えていないせいで、今の新築は出来上がった瞬間がベストの建物になってしまっています。そこはもう少し長いスパンでの『一番いいあり方とは』みたいなところを考えて行ってもいいんじゃないかと思ったりもします。
―ヨーロッパなど海外には、何百年と長い歴史を持つ建造物がたくさん残っています。それは今、渡邉さんがおっしゃったように、未来を見据えて建てているからなのでしょうか。
それもあると思います。あとは、いろんな年代の建物が同居することが日本よりもポジティブに受け入れられている気がします。新しいほどいい、みたいな価値観ではなく、いろんな時間が染み込んだものが点在していることが良しとされる文化というか。そういう違いも大きいように思います。あとは、教会が図書館になるというように、用途を変えて使い続けられている古い建物がたくさん街に溢れていることで、使い方や使う人が変わっていくことが当たり前の価値観として共有されているのかもしれません。この先、このREDO JIMBOCHOが日本におけるそうしたモデルケースになっていけば面白いなと思っています。
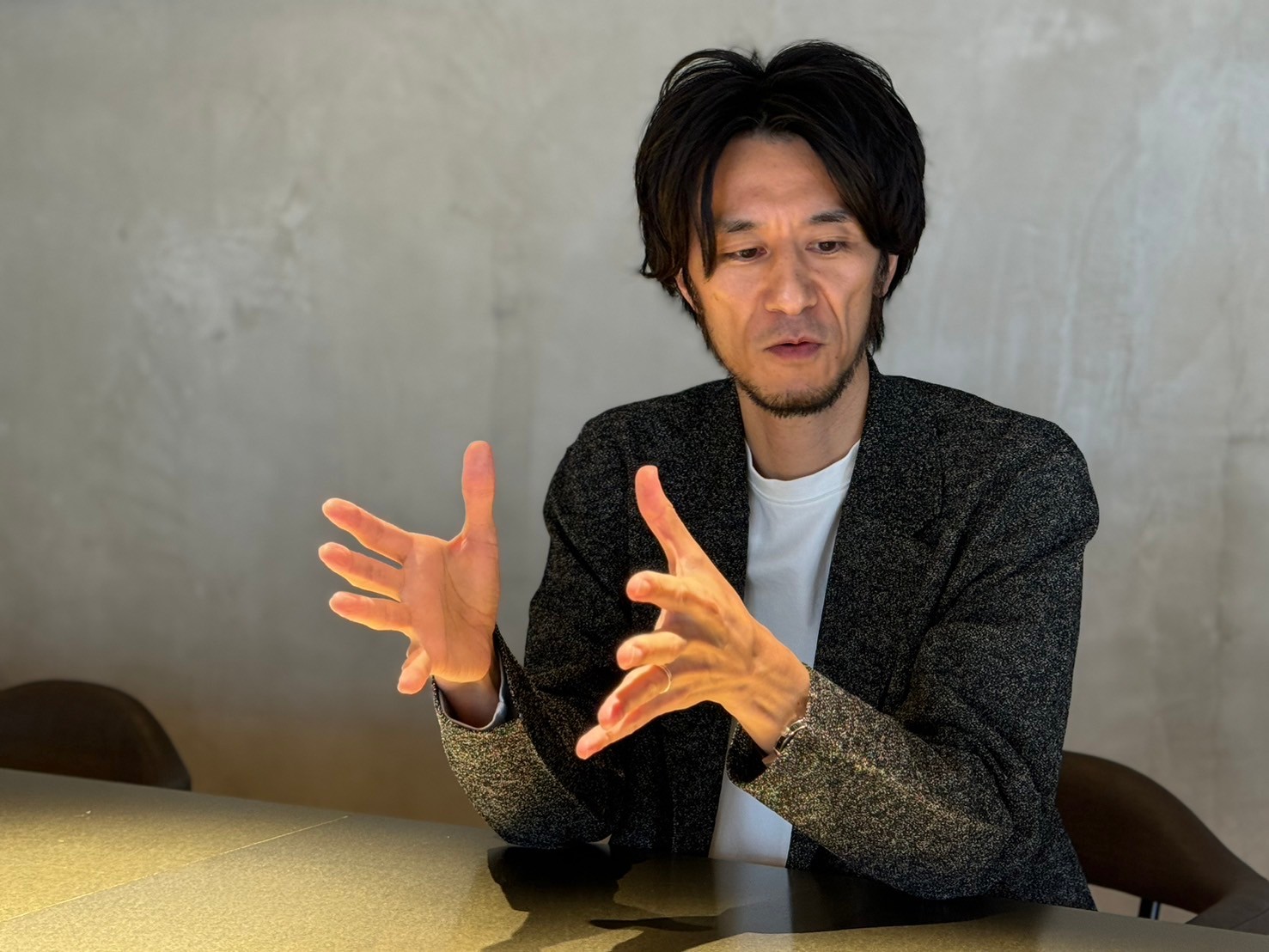 ©1981+倶楽部
©1981+倶楽部インタビュー・文/高村美砂(フリーランスライター)
渡邉明弘建築設計事務所|https://aki-watanabe.com/