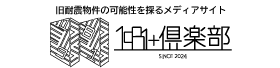VINTAGE
ヴィンテージ物件の魅力
『建物が備える素材の面白さと、偶然性を魅力に変える。』勝亦丸山建築計画 建築家/勝亦優祐・丸山裕貴
『建物が備える素材の面白さと、偶然性を魅力に変える。』
勝亦丸山建築計画 建築家/勝亦優祐氏・丸山裕貴氏
―15年にY.K.Y Design Officeを創業。その後、勝亦丸山建築計画事務所に改称し、17年に法人化されました。起業の経緯を教えてください。
丸山裕貴(以下、丸山) 僕たちは工学院大学工学部建築学科の同期で、同大学院まで通ったのですが、学生時代から、一緒にいろんなプロジェクトに取り組んだり、旅をしていたんです。卒業後は、それぞれ違う建築設計事務所に勤め、勝亦は1年で組織から離れて地元である静岡県富士市に戻って仕事を始め、僕もその3年後くらいに事務所をやめて今の形に辿り着きました。僕らの学生時代はすでに「この先はあまり新しい建物を建てられなくなる時代になる」と言われていて、僕が所属した研究室でも、建物を建てる以前の企画や運営を考えて提案するとか、社会が抱える既存の建築物をこの先どうしていくのかといった課題に焦点を当てた研究に携わっていたんです。その流れで、将来的に自分で設計事務所をするなら企画から設計、運営まで関わる仕事をしたいと思っていました。
勝亦優祐(以下、勝亦)僕もほぼ同じですが、僕は丸山以上に学生時代から建築の設計をゴリゴリするタイプではなかったんです。どちらかというと企画を立てたり、建築家がどうやって次の社会で活躍できるのかを考えるのが好きでした。建築設計をできる人間が、設計者としての専門性をもとに社会課題をいかに解決していくのかとか、設計にプラスアルファの能力を備えることでどうやってサバイブしていくのかにもすごく興味がありました。つまりクライアントありきの建築家ではなく、社会を変えるために建築家として動く必要があるなと思い、事務所設立に至りました。
 勝亦丸山建築計画 建築家/勝亦優祐氏(左)・丸山裕貴氏(右)
勝亦丸山建築計画 建築家/勝亦優祐氏(左)・丸山裕貴氏(右)―事業内容が建築設計に限らず、製造物に関するコンサルタント業や調査・企画業務に始まって、不動産賃貸管理業、店舗用什器の製造販売や輸出入、旅館業など多岐にわたるのもその理由からですか。
勝亦 正直、起業から約10年なので、個人的にはもう少し整理したいんですけどね(笑)。ただ事務所を置いているのは、僕の出身地である静岡県富士市と日本橋馬喰横山町を含む東京なので。なんとなくそこにフィールドを絞って活動しています。
丸山 実際、事務所としての最初の仕事も、勝亦が富士市で始めていたプロジェクトに僕が加わる感じでスタートしました。
勝亦 日本の各地には今も「昔は栄えていたけど、今はほとんどシャッターが閉まっているよね」という『シャッター商店街』と呼ばれる場所がたくさん残っていますが、富士市の吉原商店街もまさに、そんな感じで…。富士市に戻った時からそこに人を呼び戻す、集める仕掛けをいろいろ画策していたんです。その1つが、商店街にある立体駐車場を丸ごと借り上げて細切れにいろんな人に貸し出すという、「商店街占拠」という名のフェスの開催でした。そしたら閑散としていた商店街に、いきなり何千人もの人が集まってきて。それを見た地主さんの一人が「これだけ人が集まる可能性があるなら、この雰囲気を日常的なものにしていこうよ」と、築53年のRC4階建ての廃墟を購入されたんです。僕らはそのマルイチビルのリーシング、事業企画、設計を丸ごと任せていただきました。それが2015年だったんですけど、未だに街の人には「あそこは格好いい人が多いね」と言われるような、おしゃれな店や人が集まる場所として認知いただいています。その解体中にはアーティストさんによる展覧会企画や建築が再生されていく過程を街の人たちに周知してもらうためのイベントやワークショップも行いました。
―スタイリッシュさを携えながら商店街に溶け込んでいるのが印象的です。
丸山 一部は解体したり、内装も一旦はスケルトンにして、耐震補強も行いましたが、かなりローコストにリノベーションができたと思っています。外観も白く塗装して、窓枠も新しくしました。1階の開口部の壁がガタガタなのは、もともとその部分にシャッターがついていたから。いざ解体するとなってシャッターを外したら、外壁の部分がはつられていることに気づきました。
勝亦 きっと見えないからいいでしょ、くらいのノリでシャッターをつける際に雑にはつったんだと思います(笑)。でも、せっかくならこれを格好良く見せよう、となり、内側から見たら光がどんなふうに入るのか、手前の路地から開口部はどう見えるのか、などを考慮して、その開口部ありきで内側をデザインしました。
丸山 設計者としては、そういう偶然性が面白さでもあり、大変さでもあります。
―ヴィンテージ物件の場合、新築を建てる時とはまた違った建築技術や設計能力が必要になるのでしょうか。
丸山 そうですね。関わってくる法律も違いますし、技術面以外にも、既存のものをどこまで、どんなふうに活かせるのかといったアイデアも求められます。建物の全てにおいて『何を残して、何を残さないか』の選択肢がついて回りますしね。かといって全部を新しくしてしまうのでは既存の風合いは残らなくなってしまうので、その辺のバランスを考えながら設計できるのかは大事なポイントになります。ただ、結局は新築もリノベーションも両方できないといけないという考えは根本にあります。物件に応じて鉄骨でやる? 木造でやる? RCにする? という選択肢にリノベーションをする? が増えたくらいの感覚でいられるのが一番いいんじゃないかと。
 勝亦丸山建築計画 建築家/丸山裕貴氏
勝亦丸山建築計画 建築家/丸山裕貴氏―でなければ、マルイチビルのように壊していく過程でイレギュラーな事象が起きた時に対応できない、と。
丸山 そもそも建築は、広い知見が必要な仕事ですしね。とはいえ今後もリノベーションが主流にはなってくるはずなので。勝亦が強みにしている企画面なども絡めていかないと、例えばビルを改修しようとなった時に、施主から「一階のビルはどんな店舗がいい?」と聞かれても答えられない。一つの建物を運用するにあたって、建物を設計しただけで終わるのか、それ以外のアドバイスをできるようになるのかで、仕事の幅も大きく変わるんじゃないかと思います。
―仕事を進めていく上でお二人の役割分担はどのようにされていますか。
勝亦 僕は学生時代から図面を引くのがあまり好きではなかったのに対し丸山は好きで…いや、好きだった、か? 最近は少し嫌になっているらしいんですけど(笑)。そんなふうに、丸山は設計寄り、僕は企画寄りの人間ですが、大元の設計の思想の部分では同じものを学んできたせいか、極端な話、言葉を交わさずともプロジェクトが成立していることも多いです。意見の相違があった時も、それがどの領域にあるかによって…たとえば設計寄りなら丸山の意見を、企画のところでは僕の意見を優先する、みたいな。
―話を戻します。マルイチビルが生まれ変わったことで、吉原商店街の、シャッターを閉じていた商業ビルのオーナーさんたちが「うちも!」みたいな広がりもあったのでしょうか。
 勝亦丸山建築計画 建築家/勝亦優祐氏
勝亦丸山建築計画 建築家/勝亦優祐氏―マルイチビル以降は、住宅や店舗のリノベーション、設計から運営までを請け負われている西日暮里のシェアハウス、古民家をホテルに蘇らせた『東sui京』など様々なジャンルの仕事をされています。基本的には今後もヴィンテージ物件を中心に仕事をしていこうとお考えですか。
勝亦 例えば、馬喰横山では、UR都市機構さんと一緒に活動しているのですが、URさん自体もこの街にある6物件を買い取って、リノベーションされたり、リーシングして、新しい街のプレーヤーを入れ込んだりされていますし、僕らもそこに携わりながら、この街のウェブメディア『さんかく問屋街アップロード』の企画、運営を行ったりもしています。つまり僕らが取り組んでいるのは大きな再開発ではなく、あくまで小規模の、エリア単位でリノベーションをしながら街を活性化させ、継承していくこと。馬喰横山という問屋街のDNAを残しながら緩やかに街をアップデートしていければいいなと描いています。
丸山 馬喰横山って問屋業がメインなので基本的に商売をしている人以外が街を歩かないエリアなんです。そういう土地柄を踏まえて、たとえば設計時に「外部の人が店に入りやすいようにするにはカウンターは手前に持ってきた方がいいよね」というアイデアが生まれるのもある意味、エリア全体への理解があるからこそで…。そういう小さな連鎖を街の再生につなげていければいいなと思っています。
―これまで携った物件を含め、ヴィンテージ物件を扱う面白さをどんなところに感じていらっしゃいますか?
丸山 リノベーションってすごく手がかかるんです。先ほどお話ししたマルイチビルの開口部のように、いざ壊してみたら予想外の状態だった、みたいなことも結構多いので現場には何度も顔を出さなきゃいけない。そういった『予想外』に応じて、設計を変えたくなったり、変えざるを得なくなることもありますしね。でも人間も手のかかる子ほど可愛いのと同じで、だからこそ出来上がった物件へのテンションはすごく上がります。そう考えると、手間がかかる大変さと建物再生の面白さが常に共存していることが、結局は魅力になっている気がします。
勝亦 あとは、素材の面白さですね。要するに、価値観を変えて見ることで生まれる面白さ、みたいな感覚です。たとえばパッと見はめちゃ汚くてボロボロの古いコンクリートも、見せ方によってはすごく格好良くなる、とか。普通にプラスターボードで仕上げて塗装すれば、白い平滑な面は出来るけど、違う仕上げ方をすることでよりハイセンスなものに生まれ変わる、とか。手触りや空気の流れ、光の入り方を考慮したらもっと面白くなったね、とか。作っている過程で、一から建てる新築には絶対にありえないことが出てくるのも面白さなのかなと思います。
―新築物件とは全く別物のアイデアが問われるみたいなところも多くなる、と。
勝亦 そうですね。さっき丸山がすごく手がかかると言いましたけど、実際、設計って自由度の高い新築の方がある意味楽なのかもしれません。だから、既存の建物があることを制約だと捉えちゃうと、新築がいいなってなると思います。でも僕らはそれを素材として捉えているので。そもそもの建物が備えているものを最高の素材だと受け止めて、それをさらに磨くための挑戦だと考えることにクリエイティブさを見出している。だから楽しめているんじゃないかと思います。
―今後、こんなことをやりたいという野望はありますか。
勝亦 いっぱいあります。僕らは今、この事務所の入ったビルをはじめ、西日暮里や荻窪でもシェアハウスをサブリースで運営していますが「それならちゃんと土地を買ってやった方がいいんじゃないか」みたいな意見も結構あって。でも現実問題、東京の物件の所有権移転は、やっぱり大企業とかかなりの資本を持っている人間じゃないと動かしづらい。それに今の時代は、再開発のプロジェクトが立ち上がっても計画から完成まで20年くらいかかっちゃうんです。それじゃあ、完成した時にはもう古くなってしまっている。だからこそより早い変化を求めるにも、土地の所有権を移転させずにエリアを丸ごと借り上げて、サブリースしまくるみたいなことをしても面白いかな、と。そう思って、今、自治体や企業さんを巻き込んで話をしている最中で…頓挫する可能性もあるんですが、それもやりたいこと、やっていることの1つです。また、いろんな街づくりのプラットホームも作りたいし、2024年の1月にマルイチビルの向かいに4階建てのビルをリノベーションしたアーケードホテルを開業し、運営しているんですが、そこにいろんな資本を入れながら、ホテル周りのドミナント戦略もしていきたいと考えています。やれるかどうかは別として、やりたいことは無数にありますよ(笑)。
―この事務所はお二人で運営されているんですよね?!
丸山 ロール部分は100%リサイクル可能な紙で作られていて、接着剤やビス留めを一切せずにベルトだけで止めているので、ワンタッチでバラバラにできます。なので、傷めばすぐに修復できるし、最終的に捨てたいとなったらバラバラにして紙の部分は古紙として出せます。つまり循環し続けられる素材だけで作っています。
勝亦 家で使っているような椅子に比べると耐久年数は低いですが、イベントなど短中期くらいの用途なら十分耐久性があります。…って話が逸れましたけど、やりたいことはたくさんあるので、2025年くらいには人を増やしたいのですが、そのための時間がないという(笑)。
 勝亦丸山建築計画 建築家/勝亦優祐氏(左)・丸山裕貴氏(右)
勝亦丸山建築計画 建築家/勝亦優祐氏(左)・丸山裕貴氏(右)―丸山さんは今後、やりたいことはありますか?
丸山 ないない(笑)。もう手一杯です。
勝亦 会社としては設計チームを率いてもらうことは任せたいところですけど。
丸山 まあ、そこはなんとか、頑張ります(笑)。
インタビュー・文/高村美砂(フリーランスライター)
写真提供:和モダン一棟貸し宿 東sui京サイト|https://tosuikyo.com/