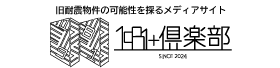VINTAGE
ヴィンテージ物件の魅力
建築士としての目線を活かして『建築』を幅広く発信。 「この業界の魅力を知ってもらいたい」。 一級建築士 × 動画クリエイター × 建築系インフルエンサー Sho建築士
建築士としての目線を活かして『建築』を幅広く発信。 「この業界の魅力を知ってもらいたい」。
一級建築士 × 動画クリエイター × 建築系インフルエンサー Sho建築士
TikTok:Sho📝建築士
Instagram:Sho📝建築士|一級建築士×動画クリエイター
YouTube:Sho建築士
note:Sho📝建築士
―Shoさんは普段から、TikTokを中心に建築を楽しく学べるショートムービーを数多く配信されています。『建築系インフルエンサー』としての活動はどのようなきっかけで始められたのでしょうか。
大学卒業後、住宅メーカーに就職してから「個人で仕事をしたいな」と思うようになったのですが、そのためにはまず、僕自身を知ってもらう必要があるなと思い、発信を始めたのがスタートでした。でも、当時はまだ動画が今ほど流行っていなかったので、最初はXで投稿を始めたんです。でも正直、鳴かず飛ばずで(苦笑)。そのうちに「これからはTikTokが流行るかも」と言われ出したのでその波に乗ってみたら、タイミングも良かったのかうまく波に乗れました。ちょうど住宅メーカーから建設コンサルの会社に転職したタイミングで、同時に副業にも力を入れるようになっていった感じです。

一級建築士 × 動画クリエイター × 建築系インフルエンサー Sho建築士氏
©1981+倶楽部
―大学は建築学科を卒業されています。一級建築士の資格も持たれていますが、本来は建築家を目指されていたのですか?
そうですね。学生時代は「いずれは住宅の設計をできる人になりたい」と思っていたので、卒業後は住宅メーカーに就職し、そこで一級建築士の資格も取得しました。ただ、その会社で、オーストラリアやインドネシアといった海外で日本式戸建て住宅の工事指導監督をしたり、施工管理を担当した中で、自分の働き方に疑問を持ってしまったというか。正直に申しますと、それぞれの国の方たちの働き方、生き方を目の当たりにして、ガツガツと仕事をしている自分に対して『これでいいのか?』と思ってしまったんです。表現が難しいですが、そこまで『仕事』に対して気負いすぎなくてもいいのかもしれない、もっと気軽に生きてもいいのかな、と考えるようになりました。
―オーストラリアやインドネシアの方たちの働き方は、同じ建築業界でも全然違った、と。
違いました。オーストラリアは特に面白かったんですけど、オーストラリアの方たちって金曜日の午後はほとんどの人が、仕事をしないで、帰っちゃうんです。もちろん、土日もお休みなんですけど。僕が一緒に仕事をしていた、建築の現場で働いていた方たちは日本の企業に勤めたことがある人もいたので、真面目に仕事をしてくださっていた方も多かったんですけど、それ以外の方たちはすごく自由でした(笑)。僕たちの会社が海外で仕事をする際には、いつもシェアオフィスみたいなところを間借りして事務所にしていたんですが、同じようにシェアオフィスを借りていらっしゃった広告系の企業の方は、いつもお昼からビールを飲んでいたし、夕方になるとさっさと仕事を切り上げて帰っていましたしね。聞けば、みなさんご家族と過ごす時間や、ご自身の余暇の時間を大事にされていて…素直に、それは素敵だなと思いました。
―インドネシアも似たような働き方ですか?
インドネシアの一般的な住宅は、レンガを積んで壁や家を作るため、結構マンパワーが必要になるんです。それもあって、オーストラリアよりは勤勉さはある気がしました。ただ、建築業界の方たちは土日も働いたり、結構勤勉だったのですが、営業の仕事をされている方などは、昼間はずっとモデルハウスの和室で横になって、携帯を触っている、みたいなことも多かったです。いつも「それで飯を食っていけるのならいいなー」と羨ましく思っていました(笑)。そんな姿を見ていたから、自分の仕事に対する考え方が覆されていったんだと思います。ただ、現実問題、食べていけるだけの収入は得なければいけないですからね。少し肩の力を抜いて働くことを求めながら、それまでと同じくらいの収入を得る方法がないか、と模索するようになったんです。ちょうどコロナ禍による緊急事態宣言で家にいる時間が増えたことも、仕事を見直すきっかけになりました。その試行錯誤の中で、最終的には今のSNSを活用した情報発信に辿り着いた感じです。

SNS総フォロワー数はなんと14万人!
©1981+倶楽部
―仕事にする以前から、SNSの活用や動画配信などには興味を持たれていたのですか?
そうですね。趣味レベルでしたが、いろんな方の配信を見るのは好きでした。当時はまだショート動画はそこまで流行っていなかったのであまり観る機会はなかったですが、YouTubeに関しては、例えばインドネシアにいるときも、トレーニングジムで体を動かしながら観ることもよくありましたし、関連書籍などを読むことも多かったです。ただその頃は、どちらかというと「自分の人生がもっと良くなるにはどうしたらいいんだろう」というような自己啓発系のチャンネルや、ビジネス系のチャンネルを楽しむことが多かった気がします。
―そこから『建築系』に特化した発信をしていこうと思われたのはなぜですか?
実は、当初は好きなことから始めようと思いグルメ系の配信をしてみたんです。インスタグラムもそうですが、過去の履歴を遡るとラーメンに関する投稿がめちゃ出てくるのはその理由です(笑)。単純にラーメンがすごく好きだったので、自分のインスタで写真と共にレビューを書いてみたり、食べログにレビューを書くような、グルメライター的なことをしていました。でもしばらく経って、似たような投稿をしている人が結構いるな、と気づいたんです。そこで、これでは勝負できないと思い、改めて方向性を考え直してみました。その際に、自分がこれまで時間をかけて勉強してきたこと、知識として持っていることは何かを考えたときに、やっぱり建築だな、と。一級建築士の資格も取得していましたしね。それもあって『建築系インフルエンサー』を志すことにしました。実際、方向性を定めて走り出してからも、建築士としての目線を持っているからこそ、似たような発信をされている方との差別化ができている気がします。
―世の中の反応はどうでしたか。
―住宅メーカーや建設コンサルの会社に勤められていた時とは違った面白さも感じられていますか。
今になって思えば、住宅メーカー時代に、戸建てよりはもう少し大きなプロジェクトの施工管理や工事全体の現場監督をするといった、全体像を見れる仕事に携われたのは、大きな経験になったとは思っています。ただ、今の方が自分自身が楽しんで仕事に向き合えていますし、今は建築土木学生カフェTONKANの公式アンバサダーもさせていただいているんですが、そこの学生さんとの出会いや、繋がりも結構刺激になっています。若い方からパワーをもらって「自分もどんどん新しいことをやってみよう!」みたいに背中を押され、アイデアが出てくることもありますしね。正直、若い方と言っても、僕が今年34歳なので、一番年齢差のある方でも1周りくらいしか違わないんですけど(笑)。でも、自分の学生時代に比べたら、今の学生は明らかに感度が高く、熱量もあって、すごく前のめりの方が多いんです。彼らに比べると、自分の学生時代が恥ずかしく感じるほどで…。でも、そんな彼らから刺激をいただくことが自分の仕事の広がりにも繋がっている気がします。
―現在はSNSの発信に限らず、ラジオのパーソナリティとして建築の魅力や業界で活躍するためのヒントを話されていたり、建築学生向けのコミュニティとしてLINEのオープンチャットも運営されています。また、9月には『東京けんちく博2025』(https://kenchuku-haku.peatix.com/)というイベントを開催されると伺いました。
―『東京けんちく博2025』というネーミングにはどんな想いが込められているのですか?
今、大阪で開催されている『EXPO2025大阪・関西万博』を見ているといろんな団体や企業が参加して「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、様々な国が思い思いの展示を行なっているじゃないですか? それってすごく楽しそうだなと思い、建築でもそんな雰囲気がつくれたら面白いかもな、と感じたんです。なので、フェスというよりは博覧会ぽいイメージを大事にしようと『東京けんちく博』と名付けました。これから毎年続けていけるようなイベントになればいいなという思いも込めて『2025』という年号も入れています。大人に限らず、中高生などで将来の進路を迷っているような方にとっても建築の面白さを知る場になればいいなと思っていますし、すでに建築業界で働いている方には建築の面白さを再認識してもらえたらいいなと思っています。ラジコンを使ってショベルカー操作をしてみたり、建築の模型を作ってみたり、体験から建築に触れてもらえるような企画も考えているので、小さいお子さんを連れて家族でご来場いただくのも大歓迎です。また『東京けんちく博2025』以外にも今後は自分が展開するコミュニティやSNSを通した繋がりを活かして、みんなで何か形になることをできたらいいな、という思いもあります。TONKANも単なる建築学生のコミュニティから発展させて、地域にいかに入り込んでいくかみたいなチャレンジを模索している最中です。
―活動の輪を広げる中で、今後、特に力を入れていきたいことや、ご自身の将来像として描いていることはありますか。
漠然とした言い方ですが、やっぱり僕は建築業界がもっと良くなってほしいと思っているんです。そこで働く人たちが自分の強みを発揮できたり、大変さはあるけど楽しく仕事ができたり、稼げるような業界になればいいなと常々思っています。そのためにも、より魅力的なコンテンツを作り続けたいし、建築業界といえばShoさんだね、と言ってもらえるくらいの業界の顔になっていきたいという夢はあります。
―ご自身が建築士として図面を引く未来はもうなさそうですか?
どうでしょう。実は、僕は今もArchi‐Prisma Design works株式会社という設計事務所に所属していて、実務に関わることも細々とながらやっているんです。ただ、今は自分が発信やイベントの事業を安定させるフェーズだと感じているのでインフルエンサーとしての活動に力を入れています。それもあって、もうしばらくは事務所と一緒に設計者としての発信の仕方を模索していきたいと思っていますが、いずれは僕自身もガリガリ図面を引いたりして理想の建築を作っていきたいと考えています。また、一口に建築業界といっても、それぞれに得意なこと、不得意なことはあって当然だと思うので、今後はそれぞれが自分の得意なところで力を発揮できるような役割分担の仕組みみたいなものも作っていけたらいいなと考えています。

©1981+倶楽部
インタビュー・文/高村美砂(フリーランスライター)