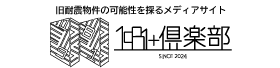1981年に導入された「新耐震基準」は、建物の耐震性を判断する基準として広く用いられてきました。しかし、その基準もすでに40年以上前のもの。旧耐震との違いや、築40年超の住宅が本当に安心かどうかを見直すことは、これからの暮らしに直結します。このコラムでは、耐震性の考え方をあらためて見つめ直します。
1. 1981年の耐震基準改正とは?旧耐震との違い
1981年6月、建築基準法の構造に関する規定が大幅に改正され、「新耐震基準」が導入されました。この改正は、1978年の宮城県沖地震の教訓をもとに行われたもので、建物に求められる耐震性能の考え方が大きく変わりました。新基準では、「中規模地震で損傷しない」「大規模地震でも倒壊しない」ことが明文化され、構造計算や設計内容も一新されました。それ以前に建てられた建物は「旧耐震基準」とされ、耐震性能に不安があると見なされることが多く、不動産の広告では1981年6月以前か以降かが明記されます。ただし、建築確認の申請時期と実際の施工時期のズレなどもあり、表記だけで一概に判断できるものではありません。

2. 築40年超の新耐震住宅は本当に安全?
「新耐震基準」を満たしている建物でも、1981年に建てられたものであれば、すでに築40年以上が経過しています。耐震性は基準だけでなく、建物の劣化状況や管理状態、地盤などの要因にも大きく左右されます。特に木造住宅や小規模な集合住宅では、外観が綺麗でも構造部分に劣化や弱点があるケースも多く、注意が必要です。築年数が経った“新耐震”住宅を所有・購入・居住する場合は、定期的な点検や耐震診断、必要に応じた補強工事を検討することが重要です。1981年以降の建物=安心と過信せず、今の暮らしに必要な安全性を見直しましょう。

3. 耐震基準とは?最低ラインを知ることから始めよう
耐震基準は、「最低限これだけ守っていれば許可します」という行政的なラインです。つまり、新耐震基準を満たしているからといって、すべての建物が“安心・安全”であるわけではありません。実際の設計や施工においては、地盤や周辺環境、用途に応じてさまざまな工夫や配慮が求められています。1981年以降も阪神・淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)など多くの大地震が発生し、そのたびに見直しや新技術が進んできました。現在の耐震設計は、制度上の基準を超える取り組みが増えており、住まいを選ぶ際には「どんな設計思想で建てられているか」「補強や点検がされているか」もチェックポイントになります。

まとめ
1981年に導入された新耐震基準は、建築物の耐震性能を高めるための画期的な制度でしたが、すでに40年以上が経過しています。制度としての「新耐震」と、現実の安心はイコールではありません。築年数や管理状態、補強歴などを確認し、必要に応じて耐震診断を受けることが、安全な暮らしの第一歩になります。