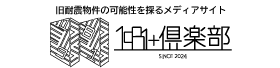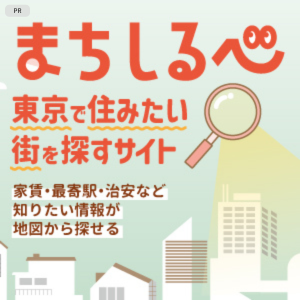旧耐震の不動産をめぐる3つの視点 ― 売却・再生・リスク対策リノベ投資成功の秘訣とは?
不動産の価値は築年数だけで判断されるものではありません。
特に1981年(昭和56年)以前に建てられた「旧耐震基準」の物件は、現代の安全基準とのズレや市場での評価の不透明さから、取り扱いが難しい資産とされています。
しかし、こうした物件にも適切な対応をすれば、資産としての価値を守ることは十分に可能です。
本記事では、旧耐震物件をめぐる課題と、その対応策を3つの視点から詳しく解説します。
1. 旧耐震基準の物件が抱えるリスクと背景
1981年(昭和56年)以前に建築された建物は、現行の耐震基準を満たしておらず、地震時の安全性に大きな不安が残ります。
特に築年数が40年、50年を超える物件では、老朽化が進んでいることが多く、以下の課題が顕著です。
・地震時の倒壊リスクが高い
・修繕や耐震補強に多額のコストがかかる
・住宅ローンの審査が通りにくく、市場での流通が制限される
さらに、建物の価値が大きく下がっても、固定資産税や維持管理費といったコストは継続的に発生します。
その結果、利用されないまま「空き家」となり、放置されるケースも少なくありません。
空き家問題が社会的な課題になっている背景には、こうした旧耐震物件の存在があります。
放置すればするほど、老朽化により解体や補強にかかるコストが増大し、資産価値はさらに下がる――。
この負の連鎖を防ぐためにも、早めの対応が重要です。

2. 相続が絡むと複雑化する理由
相続した旧耐震物件は、単なる「古い家」以上に意思決定のハードルが高くなります。
・共有名義で相続した場合の意見の不一致
・売却時に解体費を考慮するとゼロ査定、あるいはマイナス査定になるリスク
・相続税評価額と実勢価格の乖離による税負担の問題
こうした要因から、「とりあえずそのままにしておこう」という判断がなされがちです。
しかし、放置すればするほど建物は劣化し、売却の難易度はさらに高まります。
また、相続開始から時間が経過すると、権利関係が複雑になり、売却や再生の調整に膨大な時間と労力がかかるケースもあります。
こうした状況を避けるためには、「早い段階で方向性を決める」ことが何より重要です。

3. 選択肢は「売却」だけではない ― 再生という考え方
「旧耐震だから価値がない」と思い込む必要はありません。
確かに現状のままでは安全性に不安があり、市場価値も低いかもしれません。
しかし、耐震補強やリノベーションによる再生という選択肢を取ることで、物件の価値を取り戻せる可能性があります。
最近では、古い建物をリノベーションして再利用する事例が増えています。
賃貸用に活用する、カフェやオフィスに転用するなど、建物を新しい用途で生かす動きも広がっています。
特に、文化的・歴史的な価値を持つ建物なら、地域資源としての活用価値が高まり、再評価されることもあります。
大切なのは、「市場での査定額」だけで判断しないことです。
「どんな活かし方ができるか」という視点を持ち、専門家と連携して再生プランを検討することが、資産を守る第一歩となります。

まとめ
旧耐震の不動産、とくに相続が絡む場合は、判断を先送りにしないことが何より重要です。
「売却」「再生」「解体」――どの選択肢を取るにしても、早い段階で検討することで、無駄なコストやトラブルを回避できます。
もし、旧耐震物件で相続に関するお悩みを抱えている方は、1981+倶楽部までお気軽にご相談ください。
専門家の視点から、将来のリスクと価値を整理し、最適な選択肢をご提案します。