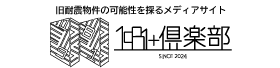検査済証なしの旧耐震物件、どう活かす?ガイドライン調査で可能性を広げよう
築年数の古い建物を活用しようとしたとき、「検査済証がない」という問題に直面することがあります。検査済証がないと、融資審査や用途変更の際にハードルが上がり、物件の活用が制限されるケースも少なくありません。しかし、「ガイドライン調査」を活用することで、こうした課題をクリアし、建物の可能性を広げることができます。本記事では、検査済証の重要性や、ガイドライン調査によって旧耐震物件を活かす方法について解説します。
1. なぜ古い建物は検査済証がない?
そもそも検査済証とは?
検査済証は、建築基準法に基づく完了検査を受け、建物が適法に建てられたことを証明する書類です。しかし、築年数の古い建物では、検査済証を取得していないケースが多く見られます。
なぜ取得されていない建物が多いのか?
検査済証の制度自体は建築基準法の施行当初から存在していましたが、当時は完了検査の受検率が低く、取得しなくても建物の利用や登記、融資が可能でした。 そのため、「完了検査を受けなければならない」という意識が低く、結果として取得していない建物が多くなったと考えられます。
また、かつては完了検査を受けないことによる行政指導もほとんどなく、建築主が特に問題を感じずに建物を利用していたため、現在でも築古物件の多くが検査済証を持っていないのが実情です。
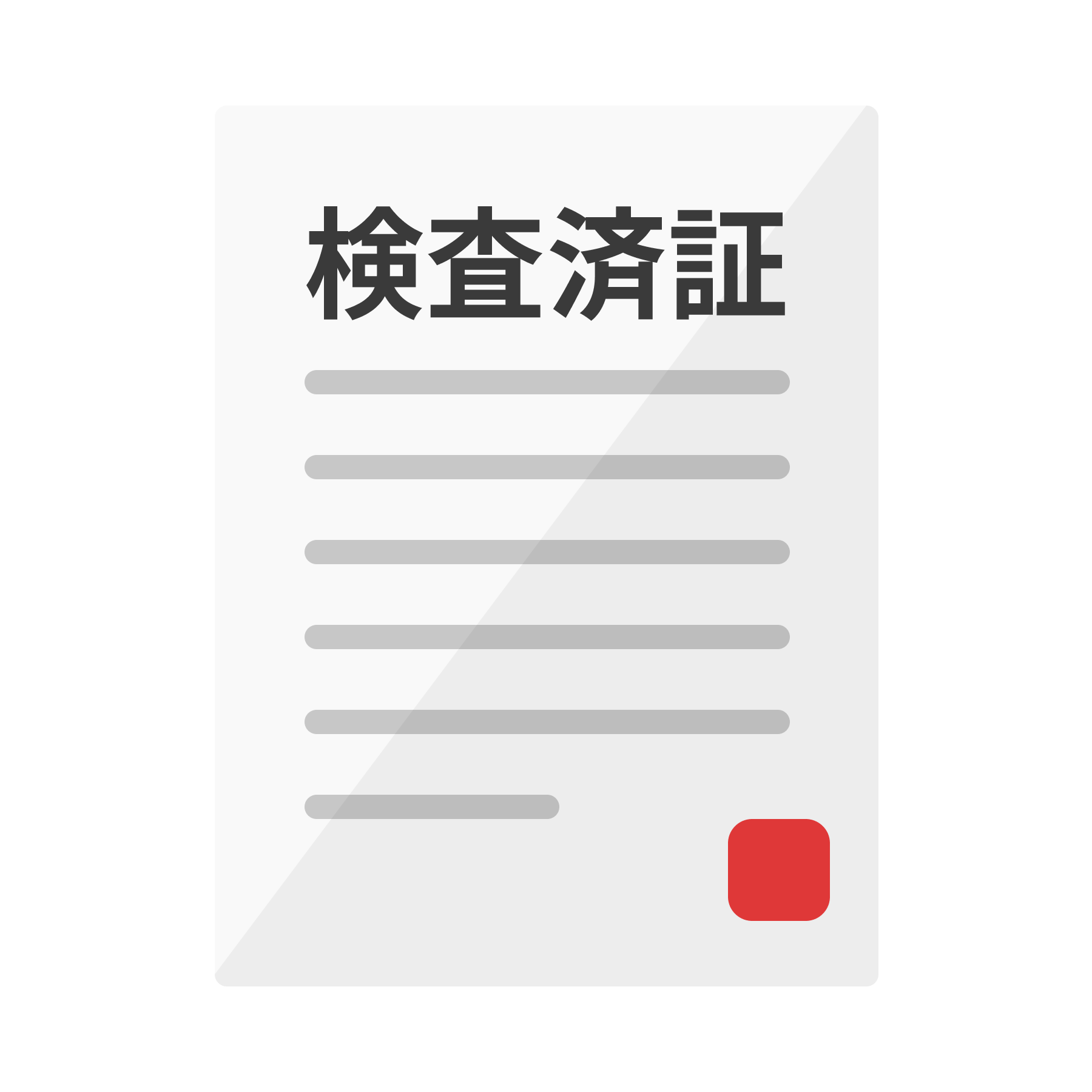
2. 検査済証がないと何が問題なの?
検査済証がないと、融資審査が厳しくなるだけでなく、増築や用途変更にも制限がかかるため、物件の活用の幅が狭くなります。
例えば、建物の用途を変更する場合、一定の規模や用途によっては確認申請が必要になります。しかし、検査済証がないと、建築基準法に適合していることを証明しづらいため、手続きがスムーズに進まないケースがあります。また、増築や改修をしたい場合も、検査済証がないと行政手続きが複雑になり、計画通りに進められないことがあります。
このように、検査済証がないことで、建物の用途変更や改修の自由度が制限されるという点は、大きなデメリットと言えるでしょう。
検査済証がなくても活用の手段はある!
しかし、検査済証が無いからといって諦める必要はありません!「ガイドライン調査」を行うことで、用途変更や改修の可能性を広げ、建物の活用の選択肢を増やすことが可能です。

3.ガイドライン調査とは?
築年数の古い建物の利活用を促進する流れの中で、国土交通省は平成26年7月に「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を公表しました。通称「ガイドライン調査」と呼ばれ、検査済証がない建物でも、建築当時の基準に適合しているかを調査し、適法性を証明するための仕組みです。
【ガイドライン調査の主な流れ】
・指定確認検査機関が調査を実施(申請者が指定機関に依頼)
・設計者が必要な資料を準備(建築図面や過去の資料が求められる)
・現地調査・書類審査を経て、報告書を作成(適法性の確認結果をまとめる)
・調査費用は有料(規模や状況により異なる)
調査の結果、建物が基準に適合していると判断されれば、用途変更や増改築の手続きがスムーズになり、融資の審査にも有利に働く可能性があります。ただし、ガイドライン調査は検査済証そのものの代替にはならず、建物の状況によっては適用が難しい場合もあるため、事前に専門家と相談しながら進めることが重要です。

まとめ
ガイドライン調査を活用することで、検査済証がない建物でも用途変更や増改築の可能性を広げることができます。
「古い建物で書類がないから仕方ない」と諦めてしまいがちですが、適切な手続きを知っている専門家に相談すれば、活用の可能性が大きく広がるかもしれません。古い建物の活用でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください!
文/西山健次(1981+運営事務局)