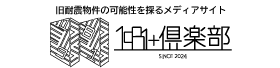VINTAGE
ヴィンテージ物件の魅力
「埋もれた価値を掘り起こし、世の中の感度を上げる」株式会社KEYBRACKET(キーブラケット)代表 菅原大輔
「埋もれた価値を掘り起こし、世の中の感度を上げる」
株式会社KEYBRACKET(キーブラケット)代表 菅原大輔氏
―今年の3月にキーブラケットを立ち上げられました。準備等々で慌ただしかったとお察ししますが、少し落ち着かれましたか。
そうですね。以前勤めていたリアルゲイトでは1年の期間をもらい退職をしたので、仕事の引き継ぎを行いながら少しずつ立ち上げ準備ができました。昨年末くらいまではバックオフィス的なところでバタバタしていたんですけど、それも落ち着いて、今はようやく業務に向かっていける状態になりました。すでに前職とは違う、新たなジャンルのご縁を何件かいただいており、順調にスタートを切れてホッとしています。
―リアルゲイトさんでは設計部長として一棟リノベーションによる不動産再生事業やフレキシブルワークプレイス事業に関わられていたと伺いました。そこに至るまではどんなキャリアを進んでこられたのですか。
また、建築を社会の問題の解決手段の1つと考えた際、他の手段も学びたいと思い、大学の仲間とCMのような広告やプロダクトの製作をつくることにも取り組んでいました。ただ、そこで少し人生に迷ってしまい、卒業後は1年間ほど就職もせずに都内で過ごしていたんです。本屋やデザイン事務所でアルバイトをしていた時期もありましたし、少しずつステップアップを図っていく中では、小さな個人設計事務所で中規模な医療福祉系の建築を設計する仕事に携わったこともありました。でも、その時に、1つのプロジェクトにおいて設計事務所が関われる範囲がすごく狭いなと感じたんです。実際、見えないところでは、事業を企画する人や我々が設計した建物を運営する人もいますが、この事務所でのプロジェクトではそこに関われる機会がとても少ないな、と。なのに、オープン後に施設が上手くいかない、などと噂を聞くと、どこか腑に落ちず…ということもあって、一級建築士の資格が取れるタイミングでリアルゲイトに転職したんです。都心の再開発の中で空室ができてしまった築20〜40年の古いビルを自社で買ったり、借りたりしながら自社で活用方法から企画し、運営まで行っている会社だということに惹かれました。また、仕事を始めてからも、僕が前職で感じていたモヤモヤ感を解決してくれるような事業の進め方をしていることに魅力を覚え、建築部門の責任者として、設計事務所や建設業の立ち上げといった組織づくりまで良い経験をさせてもらいました。

キーブラケット 菅原大輔氏
―そこからなぜ、独立してキーブラケットを起業しようと思われたのでしょうか。
大きくは3つ、理由があります。まずは、もっと幅広い人たちの感度を上げていけるような空間を作りたかったというのが1つ目の理由です。というのも、リアルゲイトは、ベンチャー企業やクリエイターなど、若い中小企業にワークスペースを提供する事業を展開していて、わかりやすくいうと華美なデザインよりも唯一無二な空間や背景のストーリー、手触りのあるような五感に訴えかける少し尖った空間が響く人たち、選択肢を多く持ちながら自分のライフスタイルのこだわりを明確に持っている感度が高い方たちをターゲットにしていました。もちろん、そういう方たちに向けての仕事もすごく面白いですが、でも世の中って、感度の高い人たちばかりじゃないと思うんです。って言うとなんだか偉そうに聞こえてしまいますが、実は僕自身もそうでした。
―むしろ、世の中は感度が高くて、ライフスタイルを明確に持っている方の方が少ないかも知れません。
まさに、そうなんです。でも僕自身も、設計の仕事を通して素晴らしい人たちに出会い、リアルな情報を得ることがきっかけで段々と自分は何が居心地良くて、何をすべきか気づいていったように思います。そう考えても、また、これからの世の中は便利さの一方で、希薄になっていくであろうそうした体験がより重要になると思うからこそ、誰かの人生のきっかけになったり、ライフスタイルの充実を喚起させたりできるような事業企画や空間を作っていきたい。なので、前職ではワークスペース中心の場の開発を行なっていましたがこれからは食や宿泊などにも幅広く関わっていこうと思っています。
また、これは2つ目の理由につながるところですが、前職では1階に雰囲気の良いカフェなど、いわゆるキーテナントを入れることが、建物価値を上げる上で重要な要素の1つでした。ですが、今後はつくるだけでなく、飲食店や宿泊施設などの運営も行うことで、コミュニティ形成を担ったり、生きたノウハウをクリエイティブ活動に活かすことを模索していこうと思っています。
そして3つ目はPRに力を入れたいと考えています。単純にその空間に来て居心地の良さを知るだけではなく、設計者や作り手のフィルターを通した事業主の想いやこだわりが建物の歴史として伝わり、見る人の解像度が上がれば、より楽しめると思うからです。その方法の1つとしてオウンドメディアを作り、建物の背景などを含めてしっかり伝えていきたいと思っています。この3つを事業として並行して行えば、世の中の人たちのライフスタイルを豊かにし、感度をあげていくためのきっかけの提供にもなるんじゃないかと思っています。
―今、抱えていらっしゃる案件はその狙い通りに進んでいますか?
そうですね。その1つ目が沖縄県那覇市東町にあるスナックビルのリノベーションプロジェクトだったのですが、そこはすでにオープンし、少しずつですが、いろんな人とのつながり、仕事の連鎖などに面白さを感じながら、進められています。
―スナックビルのリノベーションに込めた想いを聞かせてください。

沖縄県那覇市東町のスナックビル
―築34年、全6階の建物をどのように甦らせたのでしょうか。
ビルの顔であるファサードは夜のスナックビルの雰囲気を残しながら、昼は地元の人や観光客の方が通りを歩いている時に自然と入っていけるようなカジュアルな仕上げにしました。ただ、あまり爽やかな雰囲気にしすぎると、夜のスナック感が損なわれてしまいそうだったので『ネオン』をうまく使って昼の爽やかさと夜の少し怪しげな雰囲気の両立を目指しました。さらに通り沿いで販売できる露店スペースを設けることで、ビルの中の賑わいが通りに滲み出し、入居する店舗が街と繋がれるような工夫もしています。また建物の内部については、歴史を感じる、これまで利用された方たちの記憶に残っていそうな要素がいくつかあったので、そこは活かすことにしました。廊下の壁のパターンやひらがなで『ご』や『ろく』と表示された階数表示を敢えて残したのも、その理由からです。それによって長い間利用されている方が愛着を失わないように心掛けました。また、1〜4階までの既存店はそのままに、長く空室の状態が続いていた上層階は全面改修しました。6階はイベントが可能なコワーキングスペース・シェアラウンジを設け、新たな利用者がビルを訪れ『街を盛り上げる仲間が集う場所』をイメージしています。また5階は『昼夜二毛作』が可能な区画にしています。例えば、サテライトオフィスとしても利用できるし、でもそれだと人がいたり、いなかったりという状態になるので、利用者がいない時にも飲食事業などができるスペースを確保しました。
―ファサードとは対照的にコワーキングスペースは、落ち着いた雰囲気を感じます。
働く場所は、住む場所より長く過ごすこともあるスペースですからね。あまり華美な意匠にするといずれ飽きがきてしまうんです。だからこそ、空間はあまりカチッと作りすぎずに、音楽だったり、香りだったり、植物だったり、微かな変化を日常に感じられることを大事に考えました。それによって、利用者さんや入居者さんが、このスペースの『続き』を作ってくれることを期待しています。実際、コワーキングスペースとして稼働し始めた今は、完成した当初よりもグレードアップしているというか。現地のアーティストさんによるアートピースが掲出されていたり、沖縄の染め物屋さんが作ってくれたカーテンが壁にかかっていたり。運営する方や入居者さんの繋がりの中で空間に新たな発想が落とし込まれています。これは僕にとってすごく理想的というか。というのも、僕はリノベーションの際に、その建物が『リニューアル0年』にならなきゃいいなと思っているんです。リニューアルしたらまたそこから劣化していくのではなく、築34年のスナックビルであれば、リノベーションによって建物の『築35年目』がいちばんベストな状況になっていたらいいな、と。それが使い手によって36年、37年と育てていってくれるのが理想だと考えています。その部分はリノベーションにおける僕のポリシーともいうべき、考え方の軸になっている部分です。

スナックビルのリノベーション後・コワーキングスペース・シェアラウンジ
―先ほど、起業した理由として「ライフスタイルの提案」という言葉がありました。リノベーションにおいてはそこに「歴史を受け継ぐ」という思いも含まれている、と。
そうですね。実は先日、スナックビルのイベントに参加させてもらった時に、リノベーション前にクライアントが話されていたこの建物やまちづくりへの想いを、入居者さんが自然と口にされているのを耳にしたんです。それは僕にとってすごく嬉しい出来事でした。そんなふうに建物の歴史だけではなく、そこに関わる人たちの想いみたいなものが受け継がれていくことも、改めてリノベーションの良さだと感じました。
―菅原さんにとっての、ヴィンテージ物件の魅力を教えてください。
ヴィンテージと呼ばれるまで建替られずに残っている建物には、オーナー等の思い入れがある建物の場合が多く、当時の事情でできた癖のある特徴的な部分があったり、リノベーションにおける新しい素材には持ち得ない時間がつくった経年変化が魅力であると感じます。また、そこに関わった人たちの話や、建物の歴史を知ることで、使っていくうちに建物の解像度が上がっていくような感覚になれるのも僕はすごく素敵な体験だと感じています。それは新築にはないヴィンテージ物件の魅力の1つなんじゃないかと思います。
―今はまだ起業されたばかりですが、今後、新たにこういった事業をしていきたい、手掛けていきたいと考えていることはありますか。

―それだけ多角的に事業を展開されるとなると…すでにスタッフの方もいらっしゃるのですか?
いや、今はまだ一人なんです。だから、大変です(笑)。ただ、僕はリアルゲイト時代もそうでしたが、やっぱり『チーム』でやることの強さはすごく感じているので。できるだけ早くいい仲間と巡り合って、どんどん楽しいことをやっていきたいと思っています。また、今は、会社のビジョンを「うずもれた価値を掘り起こし、世の中の感度を上げる」と銘打っていますが、仕事を依頼される時にいつも思うことがあって…。それはリノベーションをする=建物自体が悪くなったということではなく、ニーズや使い方が今の時代に合わなくなったというだけな気がしています。だからこそ、建物のリノベーションに限らず、そこで何をするのかという事業の提案やどう育てていくのかも同時に行なっていきたい。つまり、僕のいう「うずもれた」というのは、ニーズがなくなってしまい埋もれてしまったという意味と、情報過多の世の中でまだ見つかっていない、これから普遍的になっていく新しい価値みたいなものという意味も含まれています。古き良さを大事にしているものの、懐古的にこだわるのではなく、トレンドやAI、デジタルといった最新のものも積極的に用いながら、皆さんに新しいライフスタイルをお届けするカルチャーキュレーションカンパニーになっていけたらと思っています。
インタビュー・文/高村美砂(フリーランスライター)
株式会社KEYBRACKET|https://keybracket.jp/