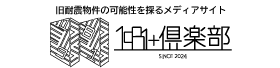VINTAGE
ヴィンテージ物件の魅力
『建物の価値を深く理解し、長期的視野で向き合う』株式会社建築継承研究所 樋口智久
『建物の価値を深く理解し、長期的視野で向き合う』
株式会社建築継承研究所 樋口智久氏
株式会社建築継承研究所|https://www.keisho-lab.jp
―価値ある建物の継承に特化した『建築継承研究所』を主宰されています。以前から、歴史的建造物に興味をお持ちだったのですか?
僕自身、幼少期は町田市郊外のニュータウンという、歴史などほとんど感じられない地域で育ちましたが、それゆえに子供の頃から古い建物が残っている街にどことなく憧れを抱いていた気がします。東京大学建築学科を目指したのも、スクラッチタイルの建物が立ち並ぶ重厚な雰囲気のキャンパスに憧れたところもありました。
そう考えると、この対照的な二つの街を行き来する中で、歴史ある街や建物に興味を惹かれていたのかもしれません。また、僕が大学生だった頃に日本の人口が減少に転じたこともあって、建築学科でも「もはや新築だけで建築を考える時代ではない」という風潮が生まれつつありました。
今となっては信じられませんが、初めて『リノベーション』が設計課題として出たのも私の学年でした。それは文京区で廃校となっていた旧元町小学校をどうするかという課題でしたが、壊すことの意味・残すことの意味を厳しく問われ、自由度が低くて難しく、非常に苦しみましたが、新築にはない面白さも感じました。今考えれば、指導される先生も手探りだったのだと思います。
そこから人口減少化時代の街や建築の姿を自分なりに考え続ける中で、文化財や歴史的建築を継承するにはどうすればいいのかを考えるようになっていきました。
意匠設計の志望でしたが、意匠系の研究室ではなく建築史研究室を選んで、3年間かけてそのテーマで修士論文を書きました。その過程では1年間、ドイツに留学してヨーロッパの建築にもたくさん触れました。ドイツに、と言いながら365日のうち100日くらいは近隣国に出掛けていたんですけど(笑)。
―ヨーロッパの建築と、日本の建築に違いを感じられたようなこともありましたか。
このご質問は俗論が多いので下手な単純化をすると怒られそうですが(笑)、地震の多い・少ないに加え、建物の構法とメンテナンス方法の違いが大きいと思います。
石や木の壁で建てたヨーロッパの伝統的な建物は、放置して傾くことはあってもなかなか倒壊までは至らないですし、撤去するのも大変ということがあって、表面的に手を加えながら使うことが自然の流れになっています。
それに引き換え、木の柱梁を組んでできた日本の伝統的な建物は時間が経つと緩み、傾きが酷くなると建具も動かなくなって使えないので、100年に一度は、解体して組み直すなど、根本的な部分に手を入れ続けないと維持ができません。
逆に撤去や移築も容易なので、古くなるとどうしても「建て替えましょう」という選択肢も候補に挙がってきてしまいます。
ただし、日本には世界最古の木造建築があることからもわかるように『木造だから短命なのだ』ということは決してありません。適切に維持されれば長持ちします。
見方を変えれば近代以降の建物は構法が異なるので、ヨーロッパや日本でも伝統的な構法とも異なる課題が出てきています。
例えば最近、私が設計を担当させていただいている『三岸家住宅アトリエ』(通称:三岸アトリエ)のような近代の建物などは、建物によって構法がバラバラで、形態が機能に特化していたりするのでどう継承していくか手法が確立されていなかったりもします。そこはこれからの課題になっていくのではないかと思っています。

株式会社建築継承研究所 代表取締役 樋口智久氏
―大学院を卒業された以降、現在の建築継承研究所を設立されるまでは、建築事務所にお勤めだったのですか。

香山先生は東大の本郷キャンパスの改修にも長く携わられていた方で、リノベーションが注目される以前から、歴史的建造物の改修設計を数多くされていたんです。
なので、私も仕事を始めるにあたって「文化財のリノベーションなどをやりたいです」みたいな話をさせていただいたのを覚えています。ですが、香山先生には「そういうことならば、君はぜひ、新築から学ぶべきだ」と言っていただいたんです。その時は「そうなのかな?」と半信半疑ながら仕事としては新築中心で実務に取り組みつつ、個人的に歴史的建造物の保存に関する勉強を続けていました。
ただ、今の自分であれば、香山先生の言葉の意味がすごく良くわかります。
つまり、昔の建物を触るからといって、昔のことだけを学んで昔と同じ方法を盲目的に用いればいいわけではありません。むしろ新築の素養がないと、建物を正しく直すことは難しいと思います。
現代の社会的要請や現代の技術を理解してこそ、過去の建物が理解でき、「建物を未来に生かすために、この部分をどう残すべきなのか」という価値判断をすることができるんだと思っています。
―その後、独立され、23年8月に建築継承研究所を設立されました。業務内容がダイレクトに伝わる事務所名にされた理由はありますか。
『この建物を良く継承したい』という想いこそが、依頼主を含むプロジェクトチームの対話の全ての基礎ですし、組織内のすべての人の目的となるものだからです。
考えが非常に多様化する現代で、当社は今までの日本の都市観を組み替えるような実践を目指していますので、一番核となる部分で他のアクターと想いを共有できる名前を選びました。
―ブランドコンセプトである『想いを街の古典に変える』という言葉にはどんな想いを込められたのでしょうか。
このコンセプトを少し言い換えますと、『想いを持って建てられた建物、維持されてきた建物を、所有者だけではなく、街にとって価値のある大切な存在(=街の古典)に変える』となります。成熟した個人主義・民主主義の先にある豊かな建築文化のあり方、価値ある建物を維持することの社会的な意義をシンプルに表現しています。
建築物の所有者は法人や個人と様々ですが『歴史的建物や価値のある建物を残す』という判断になる時点で、すでに所有者だけの価値ではなく、その場所に長く息づいてきた、周りの人からも大切に思われてきた街の共有物となっています。もちろん所有権という意味での共有物とは異なりますが、その建物の価値を街と共有すればこそ、その所有者にも巡り巡って価値が返ってくる、そんな建物のあり方を理想としています。
近年、日本には少しずつ歴史的建物の継承に価値を見出す風潮も生まれていますが、そうした理解が、今後も社会の中でより醸成されていけばいいなと思っています。
―先ほど名前が上がった国登録有形文化財の『三岸家住宅アトリエ』についても話を聞かせてください。
『三岸家住宅アトリエ』は画家の三岸好太郎・節子夫妻のアトリエとして、1934年に建築されました。ドイツのバウハウスで学ばれた山脇厳氏が設計された100年近い歴史を数えるモダニズム建築です。昨年7月に株式会社キーマン東京支社が継承されたのを機に、大規模改修工事をされることになったと伺いましたが、設計を担当される上で留意されたことを教えてください。
正直、あと5〜10年残せばいいのなら、大きく手を入れる必要はないですが、依頼主であるキーマンさんは「この先も地域で長く愛される文化財として後世に受け継いでいきたい」というご意向を持たれていらっしゃいました。
であればこそ、建物を壊さずにより良好な状態を保持しながら長期的に運営していくことを想像して、設計にあたりました。
また、建物に対する理解を深めた上で、どういった『価値』を残していくのかも大切にした部分です。この建物の象徴でもある螺旋階段は、当然残そうと思っていましたが、かと言って、築100年近い建物なので躯体が傷んでいるのは明らかでしたし、実際に歪みなども出ていました。
というのも、実は『三岸家住宅アトリエ』は西欧では鉄骨やコンクリートでようやく実現したモダニズム建築のスタイルを踏襲した建物ながら、それを木造で作ったんです。当時の日本では大規模な建物には鉄を使っていましたが、住宅レベルではとても高価だったから木造になったそうです。

三岸アトリエ(現在の玄関)
―木造とは、珍しいですね!

三岸アトリエ(2階廊下)
「こんなものを建てたい」という意思が強くあり、それを当時の建築技術でなんとか作ったということだと思います。
木造モダニズムと言われていて、当時の日本でよく作られましたが、現存する建物は少なくなってきており、非常に珍しい建物であるのは間違いありません。
と言っても、実は昭和の初期は、結構、建築技術が発展した時代でしたからね。腕のいい大工さんはたくさんいらっしゃったと想像すれば、問題は大工の技術ではありません。
私は、どちらかというとエンジニアリング面が追いついていない中で、本来鉄骨造でしか考えられないスタイルの建物を在来木造で頑張って作ったのではないか、と思っています。と同時に、その分、いろんなところに無理がかかってしまっていました。
建物の歪みなどいろんな不具合が出ていたのもその理由からです。
歴史を遡っていくと、その都度、補強として柱を外から打ちつけたり、壁を挿入したり、なんとか今まで頑張って保ってきたようですが、時代ごとに応急処置を繰り返したことで、複雑な様相を呈していました。
ただ明らかだったのは『今の形での保存を目指しても、この先50年、100年は絶対に持たない』ということだったので。それを踏まえ、耐震補強によって躯体を強化した上で、この建物が備える価値をどう残していくかに軸を置いて設計を進めました。
―樋口さんは『三岸家住宅アトリエ』にどんな価値を見出されたのでしょうか。
大きく分けて2つあって、1つは先ほどお話しした木造でモダニズムを作るということにチャレンジした建物であるということです。
また、好太郎さん亡き後は、妻の節子さんが住宅として長く過ごされたことで応接室や中庭には、南フランスの田舎のような風情を感じる、可愛らしい装飾などが随所に散りばめられていました。
モダニズムとは違う要素というか、ここに住まわれてきたご家族の時間の流れが敷地内で垣間見られるのも、建物とはまた別の価値だと受け止めていました。その2つは設計にあたっても常に頭の中に留めていました。

三岸アトリエ(中庭)
―三岸アトリエのような、歴史的建造物に携わるときは、その歴史も一から学ばれるのですか。
そうですね。建物の背景や、建築家がどういう方だったのか。どんな経緯で建つことになったのか。そこからどういう歴史を辿って今があるのかはつぶさに調べます。建物の維持に関わられたいろんな方にも可能な限り、話を聞くようにしています。
また古い建築物が今の時代に残っているということは、その都度、補修なり、改修なりに関わられてきた方もたくさんいらっしゃるはずなので。
実際、『三岸家住宅アトリエ』も、改修や維持に関わられた方に色々とお会いして「ここを直した時には、この柱や下地が相当傷んでいました。」とか「天井部分はこうやって直した」みたいな話を伺ったことも建物を知ることにも繋がり、設計のヒントにもなりました。
そういえば、前所有者の方と話をした際に「実は、壊してマンションにしようと思ったんですが、デベロッパーに依頼をしたら設計者が出てきて『僕にはこんないい建物は壊せません』と断られた」という話も伺いました。
その言葉からも分かる通り、建物が残っているということには理由があり、いろんな方の想いがあって歴史が紡がれてきた建物でもあるということも大事にしたいと思っていました。
―歴史的価値のある建物を後世に受け継いでいく上で大事にすべきことを教えてください。
価値を生かしながらも、未来の所有者の負担にならないような形でうまく維持するために、守るべきものと変えるものとのバランスを取ることだと思います。
文化財となるととたんに極端になり、触るな!変えるな!と言われる専門家の方がまだ多くいらっしゃいますが、その結果物質的には残せても、社会的には活かせられない建物が多くなってきて、まさしくいま問題になっています。
文化財というと美術館の展示物のような『静態保存』、つまり大きく手をつけずに保存し、昔ながらの姿をそのまま見せるという手法をとる代わりに、国家や地方公共団体が主に費用を負担して維持するものというイメージがありました。
しかし、税金で行うとお金のかかる保存修理しかできなくなり、財政的にも限界に達しつつある中で、公有であっても壊される文化財も出てきました。
また、観光客目当てに展示物として公開するだけでは継続性がなく、建物の維持にとって決して有効ではないこともわかってきました。そのため、文化財の活用は改修・運営も含めて民間の資金で取り組むべき課題になってきています。
この場合、収益のあげられる使用用途としつつ、長期的に維持していけるかが大事になってくるので、企画・運営の部分を一緒に考えていくのが理想だと思います。
『三岸家住宅アトリエ』も然り、文化財と聞くとどことなく「残していろんな人に見てもらえればOK」という考えに陥りがちですが、正直、それだと1度見れば終わりになってしまいます。
それでは、いずれ維持・運営も難しくなっていくでしょう。
また2025年現在、日本には『国登録有形文化財』に登録されている建物だけでも14500件ほどはありますから。
国宝を含む国指定重要文化財を中心に、『静態保存』が適切な建物ももちろん多くありますが、大多数は価値を活かしつつ、でも変えるところは変えて建物を使用しながら維持していく『動態保存』という考え方が必要になってくるんじゃないかと思います。
ただ、それをするにも先ほどお話しした何を変えて、何を残すのか、という価値判断がすごく大事になってきます。

三岸アトリエ(室内)

三岸アトリエ(旧玄関)
―建物に対する今現在の価値判断が、将来的にも継承されているのかを想像して仕事にあたるというのは、責任重大ですね。
しかし、価値ある建物に対して全て盲目的に『静態保存』の方針を取るのでは、将来世代に負担を残すことになり、建物を守ったことになりません。所有者がその重荷に耐えかねて、そうした建物の残し方全てが否定される日がきてしまうかもしれません。その兆しが見えているのが現在だという認識です。
『動態保存』を選択する場合、建物の価値を深く理解せずに所有者の判断だけで変更してしまうと、30年後、40年後に「なんでこんな変な変え方をしちゃったんだろう?」ということになりかねません。
だからこそ、僕はまず建物の『文化的価値』をしっかり理解した上で、でも、現在の社会的価値を反映して変えたほうがいいところ、変えちゃいけないところを長期的視野で想像し、建物と向き合うのがとても大切だと思っています。
未来において「ああ、こういう考え方で変えたのなら仕方ないな」と納得してもらえるかどうか。
この建物の価値を理解し、記録として残しながら改修計画を考えることが、一般的に行われるリノベーションとは根本的に異なるところだと考えています。
 三岸アトリエ(応接室)
三岸アトリエ(応接室)
―三岸アトリエの保存改修工事はいつ終わる予定ですか? 完成が楽しみです。
すでに着工していますが、今のところ、2026年度中には完成できれば、と思っています。
工事が始まってからも色々なことに直面してはいますが、それも建物の面白さと捉えながら、私自身も完成を楽しみに待ちたいと思います。
インタビュー・文/高村美砂(フリーランスライター)