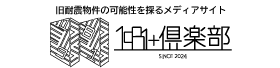VINTAGE
ヴィンテージ物件の魅力
『設計と運営を掛け合わせ、建築をデザインする』インクアーキテクツ 金谷聡史・野村拓司
『設計と運営を掛け合わせ、建築をデザインする』
インクアーキテクツ 金谷聡史氏・野村拓司氏
合同会社インクアーキテクツ|https://ink-architects.com/
―21年2月にお二人でインクアーキテクツを設立されました。どんな経緯で一緒に仕事をされることになったのですか?
金谷 もともとは、以前に勤めていた設計事務所が同じだったんです。僕はそこを16年に辞めて独立して…。
野村 その1年後に僕も独立しました。
金谷 お互い、最初は個人事業主として仕事をしていましたが、そのうち一緒にやっていこうという話になって今に至ります。
以前の事務所でお互いの仕事の仕方がわかっていた分、考えを示し合わせて仕事をしなきゃいけないことがあまりないのも良かったのかもしれません。
野村 一人で仕事をしていると仕事の幅もなかなか広がらないし、判断に迷いが出るというか。「これでいいんだろうか」「他者の言葉が欲しいな」ってことが割とあるんです。
そういう時に気心が知れていて、仕事のやり方もわかっている人が近くにいるのはありがたいです。
―仕事のやり方やデザインの方向性などが合致しているのか、みたいなことも重視されましたか。
野村 もちろん、始めるにあたっては色々と考えをぶつけ合いましたが、最終的には大きな括りでの考え方向性は一緒だろうから、大丈夫だろう、という感じでした(笑)。
金谷 というのも、我々はもともとアウトプットするデザインにそこまでこだわったスタイルがないんです。建築家の中には明確なスタイルがあって、それに興味を持ってくれたクライアントさんに設計を依頼してもらうというやり方で仕事をされる方もいますが、我々には『●●調が好き』とか『このスタイルじゃなきゃやらない』みたいなことはありません。
基本的にはクライアントさんがどんなものを望んでいるのかを軸に設計やデザインを追求していくことを当たり前に考えています。その辺のニュートラルなスタンスが合致していたのも大きかったです。
 インクアーキテクツ 金谷聡史氏(左)・野村拓司氏(右)
インクアーキテクツ 金谷聡史氏(左)・野村拓司氏(右)―前事務所では一緒に仕事をされていたということですが、そこに至るまでのキャリアについて少し聞かせてください。お二人はどんなふうに建築家を志したのでしょうか。
金谷 キャリアに関係するので少し遡ってお話しさせていただくと、僕は兵庫県神戸市に生まれ、小学5年生まで神戸で暮らしました。その後、父が脱サラして農家を始めることになり兵庫県豊岡市に引っ越したんです。そこからしばらくは田舎暮らしが続いたのですが、僕は大学進学を機に神戸に戻ってきたんです。というか、正確には大学受験に失敗したため予備校に通うためでした。その予備校は神戸市の中心街、元町の旧居留地近くにあったのですが、そこに通ううちに、都会には共用空間が多く、居場所がたくさんあるなと感じたんです。対して田舎は、土地はたくさんあるのに共用空間がほぼなく居場所がない、と。
その違いを実感した時に、何がその居場所を作っているのかを考えたら空間であり、建築であり、都市的な仕組みだと気づいたんです。それが『建築』に興味を持つきっかけとなり、神戸芸術工科大学への進学につながりました。その中では何より空間を作ることにすごく興味があったので、いずれはそういう仕事に携わればいいなと想像しながら学生生活を過ごしていました。
野村 僕は福井県福井市で生まれ、そのまま地元の福井大学に進学したんです。卒業後は、なんとなく公務員になろうかなと思っていました。
建築建設工学科を選んだのも昔から図工や美術の授業が好きだったし、周りの人たちに歴史ある学科だと聞いたから、という程度の理由です。ただ、3回生になった時に「ちゃんと設計の課題をやりたい」と思い始めたんです。でも、当時の福井大には設計を実務としている先生がいなかった。
その頃には将来は設計を仕事にしたいと思い始めていたこともあり、これは良くないと思って、大学卒業と同時に東京に出てきて東京工業大学大学院に入りました。
塚本由晴先生の研究室に入り、卒業後もその先生の事務所に入れていただき、設計の仕事をするうちに「これで生きていくしかない」と決意が固まり、その次に入ったエステック研究計画所で金谷と同僚になりました。
そこで取り組んだのが、太陽の光や熱、風などの自然の贈り物(エネルギー)をうまく活かしながら、快適かつ自由に過ごせる暮らし方ができる住宅、住まいを追求する『パッシブデザイン』で…。というかそれを勉強したいと思ったことが、エステックに入った理由だったことからも、金谷とは通じるところがあったんじゃないかと思います。
金谷 というのも、エステックの所長を務めている小玉祐一郎氏は、僕が通っていた神戸芸術工科大学時代の研究室の先生だったんです。
パッシブデザインという考え方自体はヨーロッパで生まれた考え方で、それが言語化されて学術として扱われるようになったんですけど、その小玉先生はパッシブデザインを日本に持ち込んだ第一人者でした。
僕も大学時代は、その自然の恩恵によって室内空間の快適さを得るという手法に可能性を感じて小玉先生のゼミで学んだんです。その後、象設計集団という事務所に2年間勤めたあと、僕ももう一度パッシブデザインを勉強し直しそうとエステックに移りました。
―インクアーキテクツさんが携わられた物件には常に、パッシブデザインが反映されているのでしょうか。
金谷 先ほど野村が説明した通り、冷暖房といった在来のエネルギーで室内環境を整えるのではなく、風で室内の熱を逃したり、気流で涼しさを感じるように建物をデザインするのがパッシブデザインですが、ある意味、それって特別なことではないというか。むしろ、快適な生活を求める上で至極当たり前の考え方だと思うんです。
なので、我々としては、それを敢えてテーマにすることはありません。ただ、空間づくりを考えるときには当たり前のように光の入り方や風の通り方を考慮しているので、結果的に反映されていることにはなると思います。
それは新築に限らず建物の再生事業に携わる時も同じで、リノベーションにあたってその部分の改善が必要だと感じた時には必ず、設計で改善しようと努力します。
―事業内容は、新築の設計やリノベーション、建物の管理・運営や環境に関するコンサルティング業務、土地活用のプロデュース、カフェの運営・管理など、多岐に渡ります。
ただ、我々が携わった『ハイツ自然園のリニューアルプロジェクト』(https://ink-architects.com/WORKS-13)のように、本質的な課題に遡っていくうちに自然とプロジェクトの成り立ちに触れることも多いというか。
実際、ハイツ自然園も当初は建て替えの設計者として相談を受けたんです。でも、現地を視察してみたら、正直、建築の視点からは建て替えの積極的な理由が見つかりませんでした。
そこで「建物を残す可能性を探ってみるのはどうでしょう?」と伺ってみたんです。そこから話を聞いていくうちに、建て替えを考えられていた大きな理由の1つとして、銀行の融資を受けられないといった日本の金融制度の問題が影響していることがわかりました。
でも「そこがクリアになるなら建物を残すということも選択肢にありますか?」とお尋ねしたら、もちろんだと。
建物だけではなく、庭に植えられている桜の木も残したいというご意向を伺って「では、その方法を一緒に探っていきましょう」となりました。それによって事業計画を立て、計画の妥当性を精査していく必要が出てきたので、土地活用のプロデュースや運営にまで関わらせていただきましたが、そんなふうに『設計』をきっかけに話を進めていく中で仕事が広がっていくことも多々あります。

インクアーキテクツ 金谷聡史氏
―『ハイツ自然園のリニューアルプロジェクト』は築年数、約50年の鉄筋コンクリート造の賃貸専用マンションをリニューアルされました。「街に参加する共用空間」というコンセプトを掲げられた背景を聞かせてください。
それもあってリニューアルという結論を出すにあたっては、1階をカフェにしてはどうかとケーススタディしてみたんです。この周辺は閑静な住宅地で、そういう場所がないと気づいたのも理由の1つでした。いや、以前は、建物の前のバス道沿いに、住居兼用で米屋さんや料理屋さん、タバコ屋さんなど店舗経営をされていたお宅もあったそうですが、今は住まわれている方が高齢になられたり、相続の問題などから殆どが新築マンションに変わってしまった、と。
その状況を少し寂しく感じたこともあって「共用空間の一部をカフェにすれば地域の方が自然と集まれる場所になり、地域の活性化にもつながるかもしれない」と、カフェを提案をさせていただいたんです。
野村 この場所が中目黒駅や祐天寺駅、目黒駅から徒歩15分ほどかかる、第一種低層住居専用地域の住宅街にある賃貸マンションという性質を踏まえた提案でもありました。
金谷 というのも、このあたり一帯は都市計画に基づいて、閑静な住宅街を実現している一方で、年を追うごとにベッドタウン化が進んでいるんです。その状況を考えたときに、仮にこの先も単なる賃貸マンションにしていたら、いずれ運用が厳しくなっていくんじゃないか、と想像しました。そうした長期的な視点をもとに「50年後も魅力的あり続ける場所にする」ことを目的としてこの建物の魅力を引き上げる方法を追求していきました。

ハイツ自然園1F HALO – Coffee & Moments –
 ハイツ自然園1F HALO – Coffee & Moments –
ハイツ自然園1F HALO – Coffee & Moments –
 ハイツ自然園1F HALO – Coffee & Moments –
ハイツ自然園1F HALO – Coffee & Moments –―以前は少し無機質な雰囲気の建物をポップな色合いの建物に変えたのも、それに連動した狙いがあったのでしょうか。
野村 ハイツ自然園はもともと真っ白で、特徴的な外観と重厚な佇まいが目を惹く建物でした。
ただ、周辺にはツツジやシュロの木が植えられていたものの、見た目としてもどこか寂しい雰囲気は否めずで…その印象を変えたいと思ったのが始まりでした。
そこで、まず避難動線を確保しながらも土間コンクリートをできるだけ剥がして緑を増やし、かつ分割して色を塗りわけることで、建物自体のボリュームとか圧迫感を軽減することを考えました。それを前提にオーナーさんを含めて塗り方、色を検討し、現在の色に決まりました。

ハイツ自然園(改修前)

ハイツ自然園(改修前)

ハイツ自然園(改修前)
―住宅街にあるせいか、一際、目を惹く色ですね。
野村 確かに、この一帯では特に目を惹くかもしれません。というのも、目黒区は区内全域が景観法に基づく景観計画区域で、ハイツ自然園のような少し大きめの建物を作る際に使える色が決められているんです。
なので、新たに建ったマンションなどは、殆ど無難な色しか使っていません。ただ、それによって街並みに統一感が出る一方で、それが建物の可能性を狭めているという見方もできる。
…ということを話し出すと止まらないので、ハイツ自然園の話に戻しますが(笑)、今回の色は、その景観法に基づいたギリギリの色を選びました。

ハイツ自然園(改修後)

ハイツ自然園(改修後)

ハイツ自然園(改修後)
―先ほど、この建物の建て替えの相談を受けた際には「このまま残す選択肢はないか」とご提案されたとおっしゃっていました。古い建物を再生させる価値についてはどのようにお考えでしょうか。
ただ、今回は、既存の建物を活かすことが非常に合理的だと思ったし、街との連続性、時間的な連続性、関係性を作っていく上でも、そのストーリーがすごく有効だと感じ、再生の道を選びました。
野村 実際、我々はどの物件も、いろんな可能性を探った上で、最終的に新築か、再生かの結論を出すことが殆どです。
また、ハイツ自然園の場合は大きな建物ということで、単純に壊して作るのは環境にも良くないという倫理的な側面も考慮しました。
金谷 つまりこれは、最初にお話しした「我々にはこだわったスタイルがない」ということにも連動する話で、新築を建てるのか、古い建物を残すのかということを特に目的化せず、その2つを常に平等に扱った上で、より良い選択を選んでいます。
実際、ハイツ自然園も、既存建物の設計者が相当な熱量をかけて作ったのは明らかだったし、よほどの劣化があれば話は別ですが、そうでもないのに全てを取り壊して作り替える理由はないと考えるのが自然だな、と。あとは事業計画を考えていく上で収支的に、建て替えよりリノベーションの方が40%ほど余裕が生まれるということもありました。それをオーナーさんの「この街をよりいい街にしたい」という思いに沿って1階のカフェで具現化する資金に充てたという感じです。

インクアーキテクツ 野村拓司氏
―オーナーさんの意向に応じた最適解を見つけ、リノベーションか新築か、を選択する、と。
金谷 そうですね。例えば、我々が扱った戸建ての家で『オグハウス』(https://ink-architects.com/WORKS-1)というのがあるんですが、実はそれは、ハイツ自然園とは逆に、当初はリノベーションの可能性を検討しながらも建て替えになった案件でした。
建物自体が道路にはみ出してしまっていたのと、狭小地に建つ物件で床面積も少ないため、それとリノベーションは厳しいという判断でした。
ただ、建て替えるにしても、オーナーさんの祖父母から受け継いだ土地で、近所にもご両親や親戚が住まわれているといった、人と人、あるいは人と建物の関係性にいろんなストーリーがあったので。建て替える際にはそれを引き継ぐことを心掛けました。
―外壁の鱗のような壁も印象的です。
金谷 あれも、もともとの建物の柱をオーナーさんが柿割りして割き、瓦のようにしたものを外壁に貼り付けたのですが、素材に関しては、できる限りストーリーを残せる工夫をしました。
それによって以前に住んでいた方のストーリーを感じて温かい気持ちにもなれるだろうし「この部分は自分も関わって作ったんだよ」という新たなストーリーも生まれるからです。
また、ゲストが訪れた際にはそういうエピソードを語れるかもしれないし、それがまた物語として受け継がれていけばいいなとも思っています。つまり『建て替え』や『リノベーション』は我々にとって単なる手段で、それ以上にその場所、街、人にまつわる関係づくりを大事に建築に携わりたいたいと思っています。
―今後、こういう仕事を積極的にやっていきたいと描いていることはありますか?
金谷 『ハイツ自然園』のプロジェクトは、我々としてもすごく充実感があったし、事業面でも成功例として挙げられる結果を導き出すことができました。
また、住宅街にはローカルならではの面白さがある中で、こうしたカフェを作ることで街を面白くする方法があると気づけたのも収穫でした。
それを踏まえても、今後も「建築で街を面白くする」ことには積極的に取り組んでいきたいです。
野村 先ほど少し目黒区の制度の話をしましたが、第一種低層住居専用地域というのは、都市計画上、用途に制限があるんです。
そのため、単独の店は作れない一方で、ハイツ自然園のように住居と兼用でお店をすることは許されています。その中で今回は、リニューアルの大きなネックとなっていた金融面での問題をクリアにしながら1階にコーヒースタンドというデイリーな、誰もがフラッと訪れて日常使いできる店を作れたのは、ある意味、都市計画に一石を投じる取り組みで…それは素直に良かったな、と。何より、オーナーさんの意向をもとに、住宅街に人が集える場所を作れたのも、この街や住人の皆さんにとってすごく良かったんじゃないかと思っています。
だからこそ、こうしたチャレンジは今後も模索していきたいです。
 インクアーキテクツ 金谷聡史氏(左)・野村拓司氏(右)
インクアーキテクツ 金谷聡史氏(左)・野村拓司氏(右)―リノベーションにも数多く携わられている中で、ヴィンテージ物件を購入される方にヒントとなるような、アドバイスをいただけると嬉しいです。
金谷 築古の物件を購入する目的によっても少しアドバイスは変わりますが、総合的な視点でお話しすると、今後、建物の劣化に関する技術的な課題はほぼ解決されていくと思うんです。
耐震補強の部分でも有効な手法が出てきていますし、それに応じて金融制度も少しずつ変化している状況もあります。
そう考えると、この先は、古い建物をより活かしやすい時代になっていくんじゃないか、と想像しています。
その観点からも特に大きな収益を求めない、でも、収支構造に負けない新しい価値を作ろうという時には築古物件は、そのチャレンジのハードルを低くしてくれるんじゃないかという気はします。
野村 あと、オーナーさんというのは、安く買って高く貸すのが基本だと承知の上で言わせていただくと、我々の経験上、「これで儲けよう」的な利己的な考えで購入するより、「こんなお店をしたい」というような、少し利他的なモチベーションがある方が長続きするような気はします。
金谷 利他的になりたくても、金融制度に邪魔をされて利己的になることを迫られるオーナーさんが多いのも事実なんですけどね(笑)。
ただ、ハイツ自然園のようにオーナーさんの強いビジョンと意思が結果的に銀行の考えを変えてくれた事例もあるので、そこは手前味噌ながら参考にしてもらえたらいいなと思っています。
インタビュー・文/高村美砂(フリーランスライター)