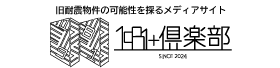VINTAGE
ヴィンテージ物件の魅力
「古い建物や空間に『付加価値』をつけて、再び人が集まる場所を創造する。」株式会社LOOPLACE 飯田泰敬
『古い建物や空間に『付加価値』をつけて、 再び人が集まる場所を創造する。』
株式会社LOOPLACE 飯田泰敬氏
―御社では築古ビル再生のセットアップオフィス『gran+シリーズ』をはじめ、既存の場を活かした不動産再生事業を展開されています。起業の経緯から教えてください。
私の社会人としてのスタートは、内装工事を行う建設現場の職人でした。16歳でこの業界に入り、天井を作ったり、壁を作ったり、床の工事をするといった内装の一部を請け負っていました。そうして下積みをしてきた中で3年後、19歳の時に他の会社に移ったら、わずか1〜2週間で職長として現場を任されるようになったんです。当時からゼネコンさんのニーズをもとに「こういうふうにしたらどうか」といった提案をするのが好きでしたし、提案までいかなくとも自分なりにあれこれアイデアを練るのが好きでした。そのうちに「自分の力を試してみたい」という思いが芽生え、21歳で独立し、個人事業主として仕事を請け負うようになったんです。その後、23歳になった1998年に有限会社成和工業を立ち上げました。その過程において、専門工事業者として内装の一部を請け負っていたところから、設計士やデザイナーを雇用してオフィスや店舗などの内装全般に携わるようになり、以来、さまざまな建築や空間づくりを行なってきました。
社名は20年1月に現在の株式会社LOOPLACEに変更しております。
―その後、16年に不動産リノベーション事業に参入されました。
内装全般に携わるようになったあと、リーマンショックの打撃を受けたことで、原状回復工事で食い繋いでいた時期があったんです。その際、ビルのリニューアルを提案した、あるオーナーさんから「そんな大きなお金は使えないから工事は必要ない。だけど、テナントはつけて欲しい」と言われたことをきっかけに「じゃあ、リニューアル工事を無償化にすればどうだろう」と考えるようになったんです。そうすれば、オーナーさんも喜ぶし、建物も生まれ変わるし、テナントも入るだろう、と。
そこから始まって、キャッシュポイントを考える中で『マスターリース契約』というオーナーとサブリース会社の間で締結される賃貸借契約を結んで業務を進めていこうという思いに至り、それが不動産部門を立ち上げるきっかけになりました。

株式会社LOOPLACE 飯田泰敬氏
―同年に始められたセットアップオフィス『gran+シリーズ』は、どのような狙いでスタートされたのでしょうか。
 gran+KANDA 使われなくなったカプセルホテルを、遊び心あふれるセットアップオフィスへ
gran+KANDA 使われなくなったカプセルホテルを、遊び心あふれるセットアップオフィスへ
実は、会社を創業した時に私が一番やりたかったのがシェアオフィスやコワーキングスペースだったんです。当時はまだそうした取り組みをしている会社はほぼなかったですが、それを求めている人は相当数いるんじゃないかと思っていました。そうしたら、しばらくして、レンタルオフィスが生まれ、今の時代では当たり前になったシェアオフィスやコワーキングスペースが注目を集めるようになって、そうだよな、と。だって、不合理じゃないですか? オフィスを借りて自分たちで内装を作ったのに、退去時にはまた全部壊して出ていかなきゃいけないというのは。マンションでは考えられない話だし、サスティナブルでもない。中国のようにスケルトンのままマンションの部屋を購入し、自分たちで内装を作るという国もありますけど、日本のマンションではまずあり得ません。なのに、オフィスだけは原状回復をして退去しなくちゃいけないわけで…ということに以前から不合理さを感じていた中で、それを形にしたのがセットアップオフィス、自社開発物件となる『gran+(グラン・プラス)』でした。
特に近年のスタートアップ企業やベンチャー企業の動きを見ていると、事業の成長スピードがとても速いですからね。それに伴う社員の増加によって必然的に2〜3年ペースでオフィスを移転しなければいけない。そうした企業向けに、セットアップオフィスはとても理にかなっていると考えました。
実際、セットアップオフィスであれば、デスクや椅子、什器、LAN配線など、ビジネスに必要なものをあらかじめセッティングした状態で引き渡すため入居時のコストを抑えられますし、退去時に原状回復をする必要もありません。
これはサスティナブルの観点からも理想的だと思っています。
―セットアップオフィス以外にも既存の場を活かした不動産再生事業に取り組まれています。築古のビルを再生して活かすことの価値をどのように考えられていますか。
少し話がそれますが、僕が若い頃、ニューヨークを訪れた際に、友人が住む高層マンションを訪ねたことがあったんです。天井が高くて窓も大きく、すごく立派な高級マンションでした。ですが、友人曰く「築年数は80年だ」と。その言葉を聞いて、すごく驚きました。
日本ではともすれば築40〜50年の建物でさえいらないものだと判断されてしまいがちなのに、80年ですからね。それを知った時に日本も将来的にはそうなっていけばいいな、となんとなく考えていたんです。当時の日本はまだ新築がいいとされる傾向が強く、中古の不動産流通比率は欧米に比べて圧倒的に低い時代でしたが、いずれは建物の価値が見直される時代がくるんじゃないか、と思っていました。それが数十年経って現実になったというか。もちろんそこには、新築マンションの価格高騰や、企業や人々のサスティナブルに対する意識の変化なども影響しているとは思います。それに、そもそも日本には『もったいない』というすごく大切な考え方がありますからね。まだまだ使えるものを簡単に取り壊すことに疑問を持つべきだろう、と。
その考えが私自身の中にも根強くあったことも、不動産再生事業に繋がっていきました。
もっとも、入居される方の安全は第一に考えるべきだし、地震が多い国だということを考慮しても、建物自体の耐久性などは都度、見直すことも必要だとは思います。ですが、新しいからいい、古いからダメだという基準で考えるべきではないんじゃないかと思っています。
―確かに昨今の不動産業界も『スクラップ&ビルド』から脱却しようという流れがあります。
そうですね。ただ、まだまだ、古くなったビルが手付かずのまま今の時代に取り残されているのも現実で…。それでも、テナントさんや入居者さんのニーズがあって、稼働しているのならいいとは思うんですよ。でも、先に例を挙げたビルのように、古さが理由でテナントが入らないということが起きてしまっているのであれば、それもある意味『もったいない』ということになってしまう。
だからこそ、私たちはそこに『付加価値』をつけることで、築古のビルを再生しようと考えました。
これは、単にお金をかけて新しいものを付け加えます、ということではありません。建物自体が持つ個性や歴史、周辺環境やその地域に住まれている方々の特徴なども考慮しながら、用途やデザインといった『付加価値』をつけることで高収益物件に再生させていきたいと考えています。

&PLACE LOOPLACEのフレキシブルオフィス
―御社が携わられている建物の再生事業では、どの物件にも「どうおもしろくする?」をコンセプトに、いろんなアイデアが盛り込まれています。それも大事な『付加価値』ですね。
その通りです。私は普段から仕事においても『付加価値』をすごく大事にしているんです。実際、社員とはいつも「自分たちが普段取り組んでいることに対して、同じことを繰り返せばいいという考えではなく、新たな工夫を加えるとか、やり方を変えてみることで『おもしろさ』を見出していこう」と話しています。
建物再生に関してもその考え方は同じで、常に同じやり方、デザインで、ということではなく、それぞれのニーズに応じて、あるいは、建物が持つポテンシャルを理解した上で『おもしろさ』を見出していきたいと思っています。それによってある時代では役目を終えた建物や空間が、再び人が集まる場所になれば理想です。
―不動産再生事業も、セットアップオフィス『gran+シリーズ』も主に東京を中心に展開されています。今後はそれを全国に、というような思いもあるのでしょうか。今後の展望をお聞かせください。
セットアップオフィス『gran+(グラン・プラス)』も、その数を増やしながら、ゆくゆくは全国展開も描いていますし、新たに宿泊事業をしたいなといった構想もあります。
いずれにせよ、弊社を設立した時から意識してきた『世の中から何を求められているのか、需要がどこにあるのか』を今後も事業の軸にしながら、弊社が持つ建築技術、時代を捉えるデザイン力、事業開発力、不動産の見立て、知見を結集させて、世の中に何を提供していけるのかということに真摯に取り組んでいこうと思います。

gran+KINSHICHO 住宅兼事務所ビルを全面リノベーションし、2区画テナント化したオフィスビルへ
インタビュー・文/高村美砂(フリーランスライター)
株式会社LOOPLACE|https://looplace.co.jp/