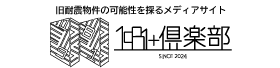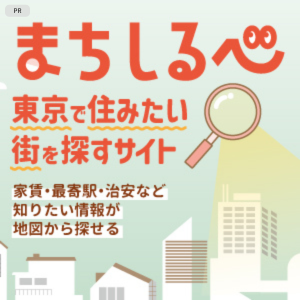助成金・補助金を活用するには?旧耐震建物の要件と耐震補強のポイント
ー 建物の改修には助成金・補助金が使える? しかし… ー
建物を改修・リノベーションする際に、多くの人が助成金や補助金の活用を考えます。
耐震補強や省エネ改修、空き家の活用など、様々な用途で国や自治体が支援する制度が用意されています。
しかし、いざ申請しようとすると、「耐震性が確保されていないと対象外」 という条件に直面することがあります。
特に、1981年以前に建てられた旧耐震基準の建物では、そのままでは助成金の適用を受けられないケースが多いのです。
では、旧耐震建物でも補助金を活用する方法はあるのでしょうか?
今回の記事では、建築関連の助成金・補助金の適用要件や、旧耐震建物でも活用する方法について詳しく解説していきます。
1. 助成金・補助金の多くは
「耐震性」が適用要件
なぜ、助成金・補助金では耐震性が求められるのでしょうか?
これは、建物の安全性が確保されていなければ、どれだけ改修をしても長期的な価値が見込めないためです。
たとえば、省エネ改修の補助金は、断熱性能を向上させたり、省エネ設備を導入することを支援するものですが、建物自体の耐震性が不十分なら、そもそも補助の対象にならないことがほとんどです。
また、空き家活用の補助金でも、旧耐震基準の建物は耐震補強をしないと対象外になる自治体が多いです。
以下に、代表的な助成金・補助金と耐震基準の関係をまとめます。
助成金・補助金の種類と耐震基準要件
耐震改修補助金(国・自治体)
・ 旧耐震建物が対象(多くは1981年5月31日以前の建物)
・ 耐震診断→補強設計→耐震改修を実施することで補助対象
長期優良住宅化リフォーム補助金(国交省)
・ 新耐震基準の建物が基本対象
・ 旧耐震建物は耐震改修を実施することが必須要件
住宅・建築物の省エネ改修補助金(省エネリフォーム)
・ 耐震性の確保が必須条件のことが多い
(旧耐震のままでは適用不可、耐震補強を併用すると対象になる場合あり)
バリアフリー改修補助金
・自治体によるが、耐震性の確保が要件になることも多い
空き家活用系補助金(地方自治体)
・ 新耐震基準であることが条件のケースが多い
・ 旧耐震建物は耐震補強をすることで対象になる自治体もあり

2. 旧耐震建物が助成金を
活用するために必要なステップ
では、旧耐震建物でも補助金を活用するにはどうすればよいのでしょうか?
助成金・補助金の申請を成功させるためには、以下のステップを踏むことが重要です。
① 耐震診断を受ける
まずは、現在の耐震性がどの程度なのかを把握することが必要です。
多くの自治体では、耐震診断に関する補助金制度を用意しており、低コストで診断を受けられる場合もあります。
② 補強設計を行う
診断の結果、耐震性が不足している場合は、どのような補強をすれば新耐震基準相当になるかを設計します。
耐震補強には、壁の補強・柱の補強・基礎の補強など様々な方法があります。
③ 耐震改修を実施する
耐震補強工事を実施し、新耐震基準相当の建物にすることで、多くの助成金・補助金が適用可能になります。
また、省エネ改修やリノベーションと組み合わせると、複数の補助金を活用できるケースもあります。

3.助成金・補助金を賢く
活用するために
旧耐震建物を活かすには、耐震補強が助成金活用のカギとなることが分かります。助成金・補助金を上手に活用するために、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
・助成金の適用要件を事前に確認する
→ 耐震性が条件になっているかどうかをチェックし、計画を立てる。
・耐震補強と他の改修を組み合わせる
→ 省エネ改修やリノベーションとセットで補助金を受けると、コストを抑えられる可能性がある。
・自治体の制度を活用する
→ 自治体ごとに異なる助成金制度があるため、地元の支援策を確認する。
・申請は着工前に行うことが多いため、事前に専門家に相談する
→ 工事後の申請では補助対象外になることがあるので、事前に計画を練る。

まとめ
耐震補強は、ただ単に「地震に強くする」ためだけではなく、建物の価値を維持し、活用の幅を広げるためにも重要なポイントです。
補助金制度を上手に活用し、「活かせる旧耐震建物」を目指してみてはいかがでしょうか?
文/西山健次(1981+運営事務局)